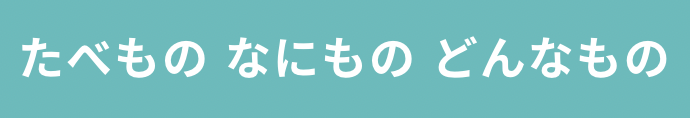味の区別がつかない人が多いなぁと感じるので、本日は「馬鹿舌(バカ舌)」「味音痴」について。
わたしは元食品メーカーで商品の企画開発職で、仕事柄味わうことにより一層敏感になりました。
その頃から意識していることを元にお伝えします!
馬鹿舌・味音痴とは。その特徴。
馬鹿舌(バカ舌・ばかじた)とは、
味そのものを感じないわけではなく、以下のような状態です。
- 味は感じるけど何の味かわからない
- 違いがわからない
- 違う味だと誤認する
他の言い方で、「味音痴」「貧乏舌」など言ったりもします。
例えば、オレンジ風味のソースがかかっているのに別のフルーツの味だと思ったりなど。

よくある話だと、
「旦那が馬鹿舌だから、良い食材を買ったりひと手間加えて料理したところで違いに気づかない」など聞きます。笑
味に無頓着なのは女性より男性に多い傾向なのかもしれませんね。
筆者も味の違いに鈍い人が非常に多いな〜と感じています。
お洒落なレストランへ行くと、食材がソースや料理のごく一部として見えない形で取り入れられていることが多いですよね。
そういう時「〇〇の味がする!」などと食べながら話すことがあると思いますが、相手の言い当てる味が違うことが多いです。
<重症レベル!?>
豆腐やモヤシが「あんまり味しない」と思っているなら、残念ながら結構味音痴の可能性が高いです。
どちらも独特な味がありますよ!
<筆者が一番驚いた味音痴エピソード>
5〜6人で食事をしていた時、居酒屋のおまかせコースの締めでカレーらしきビジュアルのものが登場。
私以外が食べ始め皆一様に「カレーだ!うまい!」と言い出し、最後に私が食べ始めたのですが・・・それは紛れもなくハヤシライスの味。
「いやこれハヤシライスだよ!」と伝えると、やっと皆「あ、ほんとだ。ハヤシかも」と気づきました。
全員お酒が入っているとはいえ、全然カレーとハヤシでは味違うのに!
馬鹿舌・味音痴は幸せ?答えはNO!悪影響やデメリット
「馬鹿舌だと何を食べたって美味しい」といわれることがありますが、それはただ”美味しい”より上の感想が出てこないだけ。
以下のような悪影響があります。
- 生活習慣病につながる
- 料理の繊細な味がわからないため、最大限に楽しめない
- 自分が料理をするときに味付けの良し悪しがわからない
馬鹿舌な人は濃い味付けを好みがち。
というか濃い味付けが習慣化していると馬鹿舌になることが多く、「馬鹿舌」と「濃い味付け」の因果関係は切り離せません。
濃い味付けを好むと、塩分や糖分のとりすぎで脂質異常症・高血圧・糖尿病などの生活習慣病につながることも。。。
他にも、料理でスパイス的に使われる味に気づきづらいので、その料理を最大限に楽しめません。(楽しめていないことにすら気づかないのですが。)
なぜ馬鹿舌・味音痴?4つの原因

馬鹿舌になる原因として、考えられるのは以下の4つです。
- 濃い味付けに慣れてしまって、鈍感になっている
- 普段から味わいながら食べていない
- ”ながら食べ”している
- どれが何の味か、考えて食べていない
子供の頃に濃い味付けで慣れてしまうと、大人になっても味の違いがわかりづらく育ってしまうと言われています。
忙しい現代、流し込むように食べているのも馬鹿舌になる原因。
普段から食べるときに「これはこういう味がするな」と食事を目で見て・舌で感じて食べていますか?
仕事をしながらや、テレビやスマホを見ながら食べるなど、”ながら食べ”になっている人も多いですよね。
普段味わって食べていないのに高級料理店に行った時だけゆっくり味わっても、急に味の区別を敏感にできるわけではありません。年間700~1000回ほども繰り返す日常食での食べ方が大事ですよ!
我が家では子供の頃、食へのこだわりの強い母から「食事中テレビ禁止」とされていました笑
ながら食べをしていなかったとしても、考えて食べていないというのもあります。
味の違いがわかる人の共通点は「どういう味がするか」をしっかり考えながら食べているということ。
「おいしい」というだけで、何も考えずに食べていないでしょうか?

好き嫌いが多い大人は、味音痴でない人が多いです!
食材や調味料の味に敏感で、好みをしっかり認識しているだけあります。
<味音痴は亜鉛不足?>
味音痴は亜鉛不足が原因、と話す方もいますが
大半の人の味音痴の原因は亜鉛不足ではなく「毎日味わって食べていない」「考えて食べていない」ことです。
食材とその味の認識が繋がっていないから、味がわからないだけ。
亜鉛不足の場合はそもそも味自体を感じずらい状態です。
実際、「この味は〇〇の味だよ」と第三者から教えてあげると「あ、それそれ!」と理解しますよね。
これは味は感じるけれど食材と紐付けられていない証拠です。
*もし突然味の感じ方が以前と変わっただとか、急に味を感じ無くなったなどあれば亜鉛欠乏や疾患の疑いもあるので病院へ行きましょう。
加齢によってもだんだん味を感じづらくなる
舌には味覚を感じる”味蕾”という器官がたくさんついており、味蕾は加齢とともに減少していきます。
30、40代になると既に子供の頃のピーク時の3分の1程度に減ってしまいます。
大人になったらコーヒーや青汁・ゴーヤを苦いと感じずらくなって飲める・食べれるようになったなどの経験がある方もいると思いますが、それは慣れのほかに加齢による味蕾の減少も関わっていることが予測されます。
ただし加齢による味の感じにくさは、「味音痴」や「馬鹿舌」と言われる状態とは異なると筆者は考えます。
馬鹿舌・味音痴を直す方法。改善・予防方法の6つのポイント

今味音痴な自覚がある人でも大丈夫!鍛えることで改善できます。
先述したように、味の違いがわかる人の共通点は
「どういう味がするか」をしっかり考えながら食べているということ。
具体的には以下の6点を行なってみてください。
- 薄めの味付けで素材の味を楽しむ
- ながら食べしない
- 「何の味がするか」考えながら食べる
- 食前に「いただきます」
- よく噛んで食べる。すぐ飲み込まない
- 外食やコンビニ弁当なら、その料理のこだわりを意識して食べる
濃いめの味付けだと、それぞれの素材の味がわからなくなってしまいがち。
薄めの味付けで素材の味を楽しむことが、味音痴改善・予防の大原則です。
もちろん濃いめの味付けのファストフードなどを食べたい日だってありますよね。いつも薄くなくても大丈夫です。
家で料理をするなら薄めの味付けを心がけましょう。
テレビ・スマホを見ながらや、仕事をしながらの”ながら食べ”は、味への意識を薄くしてしまいます。
ながら食べを止めることで目の前の食事に意識がいき、味に敏感になることができます。
ながら食べをしがちな方は、食事中はメリハリをつけてしっかり食を楽しみましょう。
これもとても大事!
食事を口にしながら、しっかり食材を目で見て、何のどんな味がするか考えながら食べましょう。
味音痴さんに大事なのは、食材と味の認識を紐付けること。
食材を視覚的に見たらわかるのが当たり前なのと同様、味覚でも食材がわかるようになりますよ。
シェイクなどの時短で済むような代替食が増えていますが、忙しいときはそういったものを活用しつつ、料理を食べるときはしっかり味わいながら。メリハリをつけて活用しましょう。
目の前の料理に意識を傾けるコツとして、食べる前に落ち着いて手を合わせ「いただきます」をすること。
これをするだけで、メリハリをつけて「今から食事を楽しむぞ!」という意識を持つことができます。
しっかり食事を味わっていない人の特徴に、早食い・噛む回数が少ないことが挙げられます。
食材の味をしっかり舌の上に滲み出させて味わう前に、どんどん飲み込んでしまうのです。
目安として20〜30回は噛んでしっかり味わいましょう。
噛むほど味が出てくる最も分かりやすい例は、白米です。噛むほど甘味を感じます。
外食やコンビニ弁当を食べるなら、メニューや弁当のパッケージに書いてある料理のこだわりポイントを意識しながら食べましょう。
それによって「美味しいなと感じる味わいは、言われてみれば確かにパッケージに書いてる〇〇の味だ」などと気づくことができます。
大切!子供の馬鹿舌予防!

子供の頃の食体験や食生活は、その人の人生にとても強い影響があります。
将来の肥満・生活習慣病の予防、より楽しく食を味わう人生のために、親御さんはお子さんの食事の味付けについて意識してみてください。
自我が出始めると食への好き嫌いもはっきりしてきて、「あれが嫌!」「これが嫌!」と言われて疲れてしまうかもしれませんね。笑
でもそれは味や食感というものをちゃんと感じている証拠。
あまりマイナスに捉えすぎず、良いことでもあるのだと思いましょう。
味を理解するために、「これは何の味かな?」などクイズをするのもおすすめです。

頑張れ!すべてのママさんパパさん!
今回の記事は私の食品開発者としての経験を元に作成しました。
いかがでしたでしょうか?
もしご質問などあれば、コメント欄にお気軽にご質問ください☆