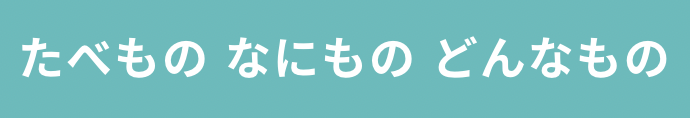本日はお盆の行事食について。
お盆は仏教の習わしで、先祖や亡くなった方が現世に戻ってくるとされています。お盆といえば、精進料理をお供えして迎えるのが一般的です。
でも「精進料理はイメージ的に作るの大変そうだし、あまり子供が好きでないものが多かったり。もうちょっとカジュアルに食べられるものはないの?」という方もいることでしょう。
本日は精進料理と、その他もう少しカジュアルに食べられるお盆の行事食を紹介します!
8月の各種行事食を知りたい方はこちら↓(即席ラーメン記念日など、面白いのがたくさんです!)
 <8月の行事食>お盆・暑気払い・焼き肉の日など、実はイベント盛り沢山!各行事の食べ物と食べ方
<8月の行事食>お盆・暑気払い・焼き肉の日など、実はイベント盛り沢山!各行事の食べ物と食べ方
精進料理とは

精進料理とは、仏教の戒律を守った修行僧の食事から始まったとされています。
仏教では肉など動物性の食品は禁止されているため、精進料理は肉や魚など動物性食品を用いない料理です。なので用いる食材は野菜と豆腐(豆)。
”精進”とは仏教では”美食や肉食を避け、粗食や菜食によって精神修養をする”という意味があり、精進料理は派手でない素材を生かした料理が多いです。
現在ではお盆のお供えものや、葬儀後の食事などが主に目にする機会でしょう。

最近は健康食としても注目されていますよ!
ちなみに筆者、仏教団体(?)が公式的に発表している精進料理のレシピを発見しました。意外と、麻婆豆腐や豆腐ステーキなどのTHE精進料理でないレシピもあり面白いです。→サイト
”THE精進料理”以外のお盆の食事
現代ライフスタイル的には、お盆は人が集まりわいわいと過ごすもの。わたしたちが食べるものについては(お供えものとは別で)もっとカジュアルで良いと思います。
精進料理以外でお供えにもされる下記の料理・食材を食卓に取り入れてはどうでしょうか?

そうめんを食べたり・お供えしたりする理由は諸説あります。
- 元々七夕もお盆行事(旧暦のお盆は七夕の1週間後)の一環で、お盆直前に諸々を清めるのが七夕だったそう。七夕でそうめんを用意する風習の流れでお盆にも連動している
- 喜びを細く長く、と縁起を担ぐ意味
- 仏様(ご先祖様や亡くなった方)が帰る時に荷物を背負う紐の意味として
- 仏様が帰る時に使う手綱として
そうめんは夏の風物詩ですし、なんといっても食べて涼しい!お盆の暑い最中に皆で食べるものとして最適です。

おはぎはお盆のお供物の定番!
- 小豆には、小豆の赤色は魔除けの効果
- 餅米には五穀豊穣(ごこくほうじょう。農作物が豊作となる願い)の祈願が込められている
また上記理由のほか、小豆は昔は特別な日に振る舞うものとされており、お盆に先祖を迎えるのにぴったりだったのです。
餡はこし餡でもつぶ餡でもOK。自分で作っても良いですし、和菓子屋さんの美味しいおはぎを買ってみるのも良いですね♪



お盆にお供えする団子には3つの種類があります。
- 迎え団子:現世へ帰ってきたご先祖様へ歓迎の意と旅の疲れを癒す意味合いの「迎え団子」。みたらしなどのタレ系や、あんこのついたお団子が一般的です。
- おちつき団子(お供え団子):代表的なのはおはぎです。
- 送り団子:真っ白な団子を用意します。これはご先祖様のお持ち帰り用で、持って帰った真っ白な団子を好きな味付けで食べてもらう意があります。
お子様と一緒にお団子作りというのも良いですね!絶対楽しいやつ!
お盆には下記写真のような、きゅうりで作った馬と、なすで作った牛をお供えします。

見たことがない人は「え?デマで騙そうとしてない?」と思うかもしれませんね。でもこれ本当です。笑
かわいいですよね。
爪楊枝を使ってきゅうりを馬、茄子を牛に見立て、ご先祖さまへ「来るときは(馬で)早く来て」「帰りは(牛で)ゆっくり帰ってね」の意味があるのです。
お供えをする仏壇のない家が多いと思うので楊枝で動物を作らずとも、お盆中の食事の食材としてきゅうり・なすを取り入れてはいかがでしょうか?

お盆に天ぷらを食べる風習ははっきりとした理由が明らかになっておりませんが、昔から天ぷらは地位の高い人や特別な機会に食べる料理。
野菜をたっぷり使う精進料理との繋がりで、たくさんの野菜を天ぷらにして皆に振る舞ったのではと言われています。
天ぷらってみんな好きですよね。普段揚げ物をしないというお家も、お盆休みに天ぷらを作ってみてはいかがでしょうか?
長野ではお盆に「天ぷら饅頭」というものを食べる習慣もあるそうです!お饅頭にてんぷら粉をつけて揚げればOKです↓
最後に
記事冒頭にも記載しましたが、お盆だけでなく8月全体の行事食・食のイベントを知りたい方は下記記事をご覧ください。
はちみつの日、ハムの日、即席ラーメン記念日など、実は8月は食の行事が盛りだくさんです!
 <8月の行事食>お盆・暑気払い・焼き肉の日など、実はイベント盛り沢山!各行事の食べ物と食べ方
<8月の行事食>お盆・暑気払い・焼き肉の日など、実はイベント盛り沢山!各行事の食べ物と食べ方