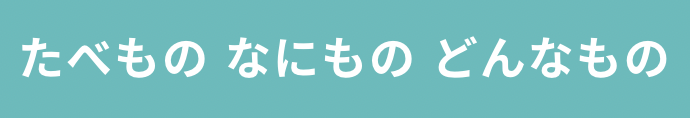11月の行事食や食の記念日を紹介していきます!11月は日本において、おいしい行事食を楽しむ絶好の季節です。
本記事では、11月の日本の伝統的な行事食や、近年できた食の記念日などを解説。
行事食や食の記念日は、保育園や学校の給食、老人ホームの食事をはじめとし、家の食事やお弁当作りのアイデアにもピッタリです。ぜひ活用してみてください。
11月1日の食の記念日・行事
すしの日は、1961年に「全国すし商環境衛生同業組合連合会」によって制定されました。新米の季節で、さらにネタになる海の幸が美味しい時期であるため、日本の寿司文化を祝います。
この日は寿司を楽しむとよいでしょう。
泡盛の日は、沖縄県酒造組合連合会によって制定されました。泡盛の仕込みが8月から9月にかけて行われ、新酒として楽しむことができる時期に、沖縄の泡盛文化を祝います。
泡盛は本格焼酎の一種で、後に紹介する「本格焼酎の日」と同日に制定されています。
泡盛の飲み方は水割りがスタンダードで、ロックも主流です。炭酸で割ったり、カクテルにしたりするのもおいしいです。

ぜひ試して欲しいのは「コーヒー割り」。沖縄ではよく楽しまれる飲み方で、全国的にも一時期話題になりました。コーヒー割りでは、泡盛をブラックコーヒーで割りコーヒーと泡盛が合わさった芳醇な香りを楽しめます!
アルコールをたくさん飲めない人でも、コーヒーに泡盛をひと垂らしするととてもおいしいので試してみてください。
本格焼酎の日は、1987年に九州の本格焼酎業者によって制定されました。焼酎の仕込みが8月から9月に始まり、新酒が11月1日前後から楽しめることから、本格焼酎を称えます。
この日は焼酎で楽しんでみるとよいでしょう。
紅茶の日は、1983年に日本紅茶協会によって制定されました。日本人として初めて外国の茶会で本格的な紅茶を楽しんだ逸話に由来し、紅茶文化を祝います。
食の行事として紅茶を楽しむなら、この日は少し高価なお茶を買ったり、お店やホテルのアフタヌーンティーでさまざまな紅茶を楽しむとよいでしょう。

本格紅茶を楽しむなら、紅茶専門店「マリアージュ・フレール」がおすすめ。同店は1854年パリ創業で、150年以上の歴史をもつフランス流紅茶専門店です。
紅茶を購入できるほか、店舗ではカフェを楽しめます。あまり知られていませんが、マリアージュ・フレール店舗で食べられるケーキ類は絶品です!
玄米茶の日は、全国穀類工業協同組合が制定。緑茶と炒った玄米を1:1で合わせたお茶を称え、健康に良いとされる玄米茶を楽しむ日です。
玄米茶には、茶葉のカテキンによる体脂肪減少効果や抗酸化作用(細胞老化を防ぐ)が含まれます。
さらに玄米にはビタミンやミネラルが摂取できるほか、γ(ガンマ)-オリザノールという成分による抗肥満作用、GABAはコレステロールや中性脂肪を抑制する作用もあります。
普段玄米茶を飲まない方も、この食の記念日を機会に飲んでみてはいかがでしょうか。
11月2日〜11月6日の食の記念日・行事
全国とうふ祭りは、全国豆腐油揚商工組合連合会が行なっています。この期間中、全国各地で豆腐製品の啓蒙活動やイベントが行われ、日本の伝統的な食品である豆腐を祝います。
豆腐の定番の楽しみ方は、冷奴、味噌汁、揚げ出し豆腐、鍋のほか、異国料理では韓国料理のチゲや中華料理の麻婆豆腐など実にさまざま!
アレンジメニューでは、半分にカットした揚げ出し豆腐の内側に切り込みを入れポケット状にした後、中にひき肉を入れてフライパンで揚げる食べ方も料理研究家の発信で話題になっています。
11月3日の食の記念日・行事
みかんの日は、全国果実生産出荷安定協議会と農林水産省が制定した食の記念日です。
語呂合わせから11月3日と12月3日を「みかんの日」とし、日本の代表的な柑橘類であるみかんを祝います。
冬のお茶の間フルーツといえば、みかんですよね。みかんはそのまま食べるほか、冷凍みかんにしたり、焼きみかんにしたりするのもおすすめです。
神戸サンド屋によって制定された食の記念日。11月3日は、サンドイッチの名前の由来とされる第4代サンドウィッチ伯爵ジョン・モンタギューの誕生日です。
また、3月13日も1の両側を3でサンドされていることから、サンドイッチの日となっています。
サンドイッチは老若男女が楽しみやすい食事の一つです。小さな子供や咀嚼の弱い高齢者などには、具材は小さめにしてサンドすると食べやすくなります。
11月5日の食の記念日・行事
いいりんごの日は、青森県が2001年に制定した食の記念日。
2001年を「りんご元年」と位置づけ、日付は「いい(11)りんご(5)」との語呂合わせから、青森のりんごを祝います。
りんごの「りん」はどこへ?とツッコミが入りそうな語呂合わせがチャーミングなこの日、ぜひりんごやリンゴジュース、りんごを使ったスイーツを食べてみてください。
11月7日の食の記念日・行事
鍋の日は、ヤマキ株式会社が制定した食の記念日。
語呂合わせ「いい(11)な(7)べ」にちなみ、鍋料理を楽しむ日です。本格的な冬の到来となる立冬の日でもあり、暖かい鍋を楽しむ季節であることにも由来しています。
 鍋の味・種類・だし40本ノック!定番、変わり種、ご当地鍋まで。今日は何鍋にする?
鍋の味・種類・だし40本ノック!定番、変わり種、ご当地鍋まで。今日は何鍋にする?
ココアの日は、1919年に森永製菓株式会社が制定した食の記念日。
11月8日が立冬に近く、体を温めるココアの需要が高まるため、ココアを愛でる日です。
カルシウム入りのココアや、食物繊維入り、睡眠の質を高めるGAVA入りのココアなどもスーパーで販売されているため、そのような機能性ココアを楽しむのもおすすめ。
また、スキムミルクをお好みで加えると、カルシウムとタンパク質を強化できる上、低脂肪ながらもミルク感を楽しめます。
あられ・おせんべいの日は、1985年に全国米菓工業組合によって制定されています。
毎年の立冬(11月7日)を「あられ・おせんべいの日」とし、米菓を楽しむ日です。
噛めば噛むほどお米の甘みを感じるおせんべいやあられ。洋風スナック菓子と比較すると油の使用量が少ないため、少しばかりヘルシーの食べられるのも魅力です。
普段なかなか食べない人も、この日は楽しんでみてはいかがでしょうか。おせんべいやあられはスーパーはもちろん、専門店で購入するのもおすすめです。
11月7日から11月21日頃までの期間が「立冬」とされ、木枯らしや冬の到来を感じる時期。
身体を冷やしやすい時期のため、この日に先述した「鍋の日」のように暖かい食事を楽しむのがおすすめです。
11月11日の食の記念日・行事
ポッキー&プリッツの日は、江崎グリコ株式会社が1999年に制定した記念日。
日付が「1111」となり、ポッキーとプリッツのPRが目的です。この日にはポッキーやプリッツを楽しむ人が多いです。
ピーナッツの日は、1985年に全国落花生協会が制定した食の記念日。11月11日は、落花生のサヤに2つの豆が双子のように並んでいることが由来です。
▼落花生とピーナッツの違い、わかりまりますか?保育園や学校給食、老人ホームでの食事を作る方なら、子どもや利用者にクイズを出してみるとよいでしょう。
 落花生とピーナッツの違いクイズ!正解したらすごい!
落花生とピーナッツの違いクイズ!正解したらすごい!
チーズの日は、1992年に日本輸入チーズ普及協会とチーズ普及協議会が制定。
当時まだチーズ文化のなかった日本人に紹介するために作られた記念日であり、現在も毎年「チーズフェスタ」が開催されています。
チーズはスーパーでも気軽に購入でき、料理にも取り入れやすいおすすめ食材。また、チーズ専門店でさまざまなチーズを味わってみるのもおすすめです。
鮭の日は、1987年に新潟県村上市、1992年には大阪市中央卸売市場の「鮭の日委員会」によって制定。
漢字「鮭」のつくりが「十一十一」となることから、11月11日が「鮭の日」とされました。
鮭は洋風料理にも、和食にも使える食材です。最も調理が簡単シンプルなものでいえば、グリル焼きやナムルが代表的。
鍋の食材とするのも、ふっくらとした魚身を楽しめおすすめです。
もやしの日は、もやし生産者協会が2012年に制定した食の記念日。もやしが縦に4本並んでいるイメージから、11月11日が「もやしの日」とされました。
もやしは安い上に、さまざまな料理に使える万能食材。この日はもやしを起点に料理を考えてはいかがでしょうか。
きりたんぽの日は、秋田県鹿角市の「かづのきりたんぽ倶楽部」が制定。きりたんぽを囲炉裏に立てて焼く様子が「1111」に見えることから、11月11日が「きりたんぽの日」とされています。
きりたんぽはお米で作られており、鍋に入れて食べるのがスタンダードな食べ方。鍋で煮る過程で柔らかくなるので、小さな子どもから高齢者まで皆が楽しめるのが魅力です。
冬の行事食としてきりたんぽを楽しんではいかがでしょうか。
全国油菓工業協同組合が11月10日を「かりんとうの日」として制定。
棒状のかりんとうが並んだイメージを「11」で表し、砂糖の糖を「10」と読む語呂合わせから、11月10日が「かりんとうの日」とされました。
口の中に入れると甘さがジュワッと広がるかりんとうをぜひ楽しんでみてください。
11月13日の食の記念日・行事
川越いも友の会が制定。「栗(九里)より(四里)うまい十三里(9+4=13)」という言葉からきており、江戸から十三里離れた川越のさつまいもがおいしかったことに由来します。
できるならば屋外でさつまいも焼きができると、秋を楽しむにぴったり!
料理では、さつまいもご飯、さつまいもチップス、バター醤油煮、大学芋などがおすすめです。
11月15日前後
七五三といえば、子供たちの成長を祝う日。
赤飯、鯛の姿焼き、煮物、茶わん蒸し、お吸い物などが一般的な七五三の行事食メニューです。千歳飴も購入すれば、もう完璧!
フランスの新酒ボジョレー・ヌーヴォーは、毎年11月の第3木曜日に解禁され、それ以前に販売やサービスが禁止されています。
この日は、新しいワインを楽しむ日です。
11月17日の食の記念日・行事
茨城で1994年(平成6年)に全国の生産者が集まって、「れんこんサミット」が開催されたことから制定されました。
レンコンはポリフェノールを豊富に含み、ビタミンCと食物繊維もたっぷり。
またサクサク、ザクザクとした食感は食べ応えがあり、しっかり噛むことで満腹感を得やすいのも健康食材としてのポイントです。
あまり普段料理で使わないという方も、ぜひこの日はレンコンを料理に取り入れてみるとよいでしょう。
11月20日の食の記念日・行事
「いい乾物の日」という食の記念日は、日本かんぶつ協会が制定し、かんぶつの普及啓蒙活動を行っています。
かんぶつと一言に言ってもさまざまで、身近な食材ではわかめ、切り干し大根、ドライフルーツ、干し椎茸、にぼし、乾燥コンブなどがあります。
長期保存できるため自宅でストックしておくと便利な乾物。「あともう一つ具材を入れたいな」という時のお助け食材にもなります。
ピザ協議会が制定。日付はイタリア王妃マルゲリータの誕生日からきており、ピザの普及を目指す食の記念日です。
この日はピザのデリバリーのほか、自宅でピザ作りを楽しむのもよいでしょう。
保育園や老人ホームであれば、皆でピザ作りをするイベントができると盛り上がること間違いなし。
また、「自宅で焼きたいけど、ゼロから作るのは面倒」という方には、焼くだけの冷凍ピザがおすすめです。
11月21日の食の記念日・行事
1970年11月21日は日本国内のKFC1号店「名西店」(現在は閉店)がオープンした日。それにちなんで11月21日はフライドチキンの日とされました。
フライドチキンを頬張るのって、わくわくしませんか?
保育園や学校給食、老人ホームの食事であれば、フライドチキンを提供した食事タイムに「今日は何の日?」クイズをするとよいでしょう。
11月22日の食の記念日・行事
小雪は11月22日から11月23日にかけての節気で、「雪が少ない」という意味を持ちます。雪が降り始める季節を指します。
小雪では決まった行事食はありませんが、ここから一段と寒くなってくるので、暖かい料理を食べましょう。
11月24日の食の記念日・行事
ユネスコ無形文化遺産に登録された和食を、次世代へ継承する日です。和食給食の普及など、和食文化を促進する活動が行われます。
11月29日の食の記念日・行事
宮崎県の「より良き宮崎牛づくり対策協議会」が制定。語呂合わせから、「いい肉の日」としていい肉の魅力をアピールするために作られた日です。
この日はスーパーの生肉売り場や焼肉店でお肉がお買い得になっていることが多いので、お肉を楽しむとよいでしょう。
11月30日の食の記念日・行事
本みりんの良さを広めるために全国味淋協会と全国本みりん協議会が制定。語呂合わせで「本みりんの日」とされており、本みりんのPRが行われます。
11月の行事食や食の記念日で食事を楽しもう
11月の行事食や食の記念日を紹介しました。
本記事で紹介した食のイベント類は、自宅での料理や、学校、保育園、老人ホームなどの食事の場でも、その日の料理ネタやイベントとして活用できるでしょう。