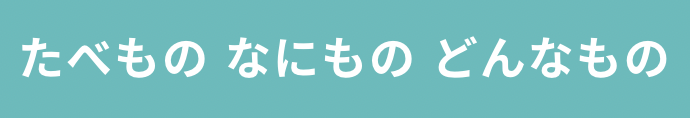日本茶スペシャリストで茶道裏千家中級のたしろです!
ペットボトルのお茶に「玉露入り」と謳われていたりと、何かと玉露を目にする機会があるはず。その時、玉露とは何なのか、煎茶との違いをふと疑問に思うことがあるかと思います。
煎茶との違いを含めて、玉露を解説します!
玉露と煎茶の違い

玉露は、収穫数週間前からあえて日光を遮ぎる「被覆栽培」をすることで、うま味の元となるアミノ酸が苦味成分に変わるのを防いだお茶です。
それにより強い甘味とうま味があり、喉を潤すためというより楽しむために飲まれる上級茶です。
| 煎茶 | 玉露 | |
|---|---|---|
| 用途 | 喉を潤すための常用が多い | 楽しむためのもの |
| 栽培方法 | 収穫まで日光にあてる | 被覆栽培で収穫数週間前から日光を遮る |
| 味わい | 甘味・うま味・渋味(苦味)のバランスがよくスッキリとした味わい | 甘味とうま味が強い。とろみを感じさせるものもある |
| 淹れ方 | 70~80℃で1~2分 高温で短時間 | 50~60℃で2〜2分半 低温でじっくり |
| 成分 | テアニン(うま味)、カテキン(渋味)等バランスよく存在 | 煎茶と比較してテアニンの割合が多め・カテキンの割合少なめ |
煎茶のように大量生産向けではないため、一般的には煎茶より玉露のほうがお値段も高いです。(もちろん、煎茶にも高品質・高価格なものもあります!)玉露の味わいは、海藻を想起させる独特な香り・うま味を感じます。とろみがあるように感じることもあります!
また煎茶とは淹れ方も異なります。煎茶は高温で短時間さっと淹れるのに対し、玉露は低温でじっくりと抽出します。
玉露の栽培方法「被覆栽培(ひふく栽培)」

収穫まで日光を浴びせる煎茶と異なり、玉露の栽培では収穫の20日ほど前から藁やヨシズなどで茶樹を覆い、一時的に日光を遮る被覆栽培(ひふくさいばい・別称「覆い下栽培」)を行います。
被覆栽培によりうま味のもとであるアミノ酸テアニンを多く含み、逆に苦味や渋味を感じるカテキンを抑えたお茶になります。
煎茶は外で元気いっぱいお日様を浴びて育った子、玉露は日焼けしすぎないよう育てられたお嬢様のイメージです。
玉露の特徴(味・香り・色)

煎茶と比較し、強い甘味とうま味・まろやかさが特徴です。舌の上で転がすと海藻を想起させるような独特な香りとうま味を感じます。とろみがあるように感じることもあります。
この独特な香り・味は被覆栽培から生まれる特徴のため、「覆い香(おおいか)」と呼ばれます。

煎茶は甘味・うま味・苦味・渋味をバランスよく含み、すっきりとした味わいです
製造した茶葉は、煎茶より太めの傾向。質が良いものほど淹れた時に透明感があります。
簡単シンプル!玉露の淹れ方は5ステップ

肩肘張らずに始めていただきたいので、特別な道具がなくてもできる手軽な方法をご紹介します!

まずは何度か試してみて、本格的に行いたくなった際には食品用温度計を買うと温度調整が楽になります。
お湯の量:一人分につき15ml ※量が少ないので茶碗も小さめだと尚よし!
茶葉の量:一人分につき2~3g
基本手順:
- お湯を沸騰させる
- 50~60℃までお湯を冷ます(簡単にお湯の冷ます方法)・茶碗を湯で温めておく
- 葉を急須・茶漉しに入れる
- お湯を注ぎ、2~2分半ほど蒸らす
- (複数名分の場合)各茶碗へ少しずつ廻し注ぎ、均等に注ぐ
お湯を冷ますには、器にお湯を移すと楽!
器に移す度に約5~10℃下がると言われています。沸騰時が100℃なので玉露の場合はおおよそ5回ほど器に移すイメージ。
ただ、室温などにもよるので調整してください。冬で器や室温が冷たくなっている場合は4回ほどで大丈夫です。
茶碗や急須にお湯を移す作業をすれば、茶碗や急須自体も温まるため、予定外にお茶が冷めて出来上がってしまう心配もなくなります。

茶碗や急須にお湯を移す作業をすれば、茶碗や急須自体も事前に温めておけます!
上記はあくまで基本のやり方。茶園やメーカーによって品種や製法が異なりますので、購入した茶葉に応じてパッケージに記載の淹れ方に準ずるのがおすすめです!
玉露は煎茶など他の日本茶と比較すると、とろみすら感じる濃厚な味。
うま味であるアミノ酸は50~60℃近辺の比較的低温で抽出され、渋味・苦味であるカテキンは80~90℃の高温で抽出されます。
そのため、うま味を味わう玉露は低温でじっくりと淹れるわけです!
玉露はカフェイン量が多い
マイルドな味わいの玉露ですが、意外とカフェインが多いです!100mlあたりのカフェインはコーヒーより多いと言われています。
玉露は高級茶として若い芽を使うのがメインであることが、カフェインが多い理由です。若い芽はカフェインが多い傾向です。
玉露はカフェインの点でも、大量に飲むのではなく、嗜好品として楽しむ高級茶という楽しみ方がちょうど良いです。
一方の煎茶は高級品というより普段使いを目的に大量に生産するため、若い芽だけでなく少し育った芽を使うことが多いです。もちろん。茶園ごとの方針や銘柄にもよります
玉露の代表的産地
玉露は下記2カ所が特に有名な産地です。
- 福岡県 八女茶(やめちゃ):玉露の生産量全国1位。県南東部の八女市周辺で栽培されています。一般的にはお茶は春になると一番茶・二番茶・三番茶・・・と順番に収穫され、一番茶が最も上級とされています。八女茶はほとんどの茶園が二番茶までしか刈らず、翌年の一番茶が美味しくなるよう茶樹に栄養を蓄えさせています。
- 京都府 宇治茶(うじちゃ):京都府南部の宇治市周辺。この辺りは抹茶と玉露の栽培がメインで、量を生産するより品質重視の指向です。
〜余談〜 玉露の茶殻は食べられる
これは余談ですが、玉露の葉はとても柔らかいため茶殻も料理にして食べられます。
食べることが大好きな食いしん坊なのでつい、食べれないか?という思考が・・・。笑
ご飯に混ぜたり、おひたしにするなどがあります。