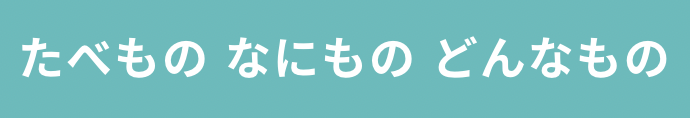こんにちは!日本茶スペシャリストのたしろです!
本日はお茶の種類について紹介していきます。「お茶」や「日本茶」と一言に言っても煎茶、玉露、抹茶、ほうじ茶などいろいろあります。
回転寿司で出てくるあの粉末の美味しいお茶、何というお茶の種類か知ってますか?
答えは「粉茶」。規格外のお茶の集まりから作られているんですよ!飲むとスッキリしていいですよね。
他にも色々と種類があるので見てみましょう!
日本茶スペシャリストの教材を元に紹介しています。資格検定を受ける方にもぜひ参考にしていただければ幸いです!
日本茶の種類一覧(ひとこと説明付き)
- 煎茶(普通煎茶・深蒸し煎茶・特蒸し茶)
- 玉露 :特殊な栽培方法でうま味と甘味UP
- かぶせ茶(冠茶) :煎茶と玉露の中間の味わい
- 釜炒り茶 :釜炒りの製法で香ばしい
- 蒸し製玉緑茶(グリ茶) :茶葉がグリッと勾玉状
- 抹茶 :特殊栽培で育て、臼で粉末状にした茶
- ほうじ茶 :色が変わるまで焙じた
- 玄米茶 :炒り豆と茶葉のブレンド
- 番茶 :定義複数あり
- 製造段階で生じる各種茶
▼一番疑問として多い玉露と煎茶の違いについては、こちらで詳しく説明しています!
 玉露とは?煎茶との違い・簡単な淹れ方・カフェインの多さなど解説!
玉露とは?煎茶との違い・簡単な淹れ方・カフェインの多さなど解説!
煎茶(普通煎茶・深蒸し煎茶・特蒸し茶)

最もお馴染みなのは煎茶ですね。実は煎茶の中にも種類があります。
一般的に煎茶といえば普通煎茶のことを指し、普通煎茶より製造工程の蒸し時間を長くしたのが深蒸し煎茶、さらに長くしたのが特蒸し茶です。
煎茶(普通煎茶)
日本で最も馴染み深いお茶。
- 蒸し時間30~40秒(製造工程での蒸し時間)
- 上質なものほど、茶葉が色鮮やかで艶がある。葉もピンっとする
- お茶として淹れると黄色〜黄緑色、爽やかな香り、甘味・渋味・苦味・旨味のバランスが良い
深蒸し煎茶
煎茶より製造での蒸し時間が2~3倍長い。
- 煎茶より蒸し時間が2~3倍長く、蒸し時間1~2分
- 蒸し時間が長いのでその分渋みや苦味が抑えられ、まろやかな味わい
- 茶葉が製造中に砕けやすくなり、普通煎茶と比べると粉や細かい葉が多い
- 味が濃くまろやかで、濁ったお茶
※粉感が苦手な人もいます。
特蒸し茶
深蒸し煎茶よりさらに蒸し時間を長くした。
- 明確にどれぐらいの蒸し時間が特蒸しちゃとは決まっていないが、深蒸し茶より長く蒸したものを特蒸し茶と呼ぶことが多い。蒸し時間はメーカーや茶園で異なる。
- 長く蒸すことで繊維がほぐれ茶の成分が非常に出やすい
- 普通の煎茶とは随分と異なった濃いお茶
玉露
被覆栽培という栽培方法でできた、強い甘味とうま味のお茶。
- 強い甘味とうま味を持つ。日本茶の中でも最上ランク
- 喉を潤すため < 楽しむため
- 覆い下栽培(被覆栽培)によって生まれる「覆い香」という香りと味がする
- 茶葉は煎茶より太め、質が良いものほど淹れた時に透明感がある
- 京都の宇治、福岡の八女茶などが有名
茶摘みの20日前のあたりに藁やヨシズなどで茶園を覆い、一時的に日光を当てない栽培方法。
これによって旨味成分が苦味成分に変わるのを防ぐ。

「覆い香」は玉露独特の風味。
しばらく下の上に置いておくと海苔を思わせるような独特な香りとうま味。
優雅な気分に♪
かぶせ茶(冠茶)
短めに被覆栽培をした、煎茶の苦味+玉露のうま味 を併せ持つお茶。
- 玉露で行う被覆の時期を1週間〜10日に縮めた(=うま味が苦味に転じる分と、転じず残る分が混在)
- 淹れ方で2通りの味を楽しめる
- ぬるめのお湯でじっくり・・・玉露感(うま味強め)
- 熱めのお湯でさっと・・・煎茶感(渋みを伴う爽やかさ)
- 三重県がかぶせ茶の出荷量No.1
釜炒り茶
他のお茶が製造工程で蒸すのに対し、炒る製法をとった香ばしいお茶。
- 釜で炒ることで発酵を止める(他の茶は蒸すことで発酵を止める)
- 煎茶は製法の最後に精揉という葉の形を整える工程があるが、釜炒り茶には精揉の工程はない。そのため葉が勾玉状にカールしている
- 淡い黄色のお茶。香りの高さ◎
- 炒ることで青臭さが消え、香ばしい釜香が出る
- 産地は主に九州。宮崎の高千穂、佐賀の嬉野
蒸し製玉緑茶(グリ茶)
茶葉の形を整える”精揉”の工程を取らず、茶葉が勾玉のように丸まったお茶。
- 勾玉状の形状(煎茶は最後に茶葉をまっすぐにするために精揉するが、蒸し製玉緑茶はしないため)
- 勾玉状でグリッとした形になるので「グリ茶」とも呼ばれている
- 釜炒り茶よりもやや緑色が強い。黄緑色
- 普通煎茶と比べて渋味が控えめでまろやか
- 九州と静岡の一部がメインの産地
抹茶
被覆栽培を行い、蒸したら揉まずに即乾燥。臼で粉末状にしたお茶。
- 製法:被覆栽培→蒸す→揉まずに乾燥。この状態を碾茶(てんちゃ)と呼ぶ→碾茶を茶臼で細かく挽いて粉末状にした
- 粉末状になる前のものを碾茶(てんちゃ)といい、抹茶を「碾茶」と呼ぶことも
ほうじ茶
お茶を褐色になるまで焙じて作るお茶。
※「焙じる」とは=火で炙ってカラカラにする。(「炒める」というのは油を使う)
- 茶葉の水分がなくなるまで炒る。
- そのため各種成分が減り、渋味や苦味も減る
- 刺激が少なく子供やお年寄りにも向いている
- ほうじ茶はお茶本来の味を減らすことが前提となるので、番茶や下級煎茶、茎茶などランク低めのお茶を用いることが多い

わざわざほうじ茶用の茶葉を買わなくても、煎茶などをフライパンで炒って自作できるのも魅力!
玄米茶
茶葉と炒り米をブレンドしたもの。(=1:1が基本)
炒り米を使っているので香ばしい香りが漂い、和食の食事と一緒に飲む用としても良く合います!
茶葉を煎茶や深蒸し煎茶、抹茶にしたりとバリエーションが多数あるのも玄米茶の魅力。
※炒り米は玄米でなくとも白米やもち米を使うケースもあるが、それらも玄米茶という
番茶
「番茶」という呼び方は明確な定義を決められておらず、下記の様々な状態を指す。
一般的にお茶は茶葉の摘み取る順番で、最初の収穫を一番茶、それに次いで二番茶、三番茶・・・と呼ぶが
- 一番茶と二番茶の間に積まれた”番外のお茶”
- 三番茶以降の遅く摘まれた”晩茶”を転じて番茶
成長具合を確認するために途中で摘み取ったものを集めたものだったり、遅いタイミングで摘んだりする。かつ製法の定義もなく様々なパーツが混ざる。
製造段階で生じる各種茶の名前
荒茶(あらちゃ)・出物(でもの)
日本茶製造では、発酵を止めるために蒸すor炒ることで加熱する。
加熱工程の直後は、細かかったり小さかったりで十分にお茶を抽出できない規格外のものも多い。これは雑味の原因になるため取り除くのだが、この色々混ざった状態を「荒茶(あらちゃ)」と呼ぶ。
荒茶はふるいにかけられ、規格内のものと不要部分「出物(でもの)」に分ける。
※これはそのまま飲む茶の名前ではなく、製造段階での名称です。本格的に日本茶の勉強をする方は大切になってきますので「荒茶」「出物」も覚えておいてください。
茎茶(くきちゃ)
出物の茎部分は茎茶(くきちゃ)になる。
- スッキリとした甘味
- 有名なのは石川県の「加賀棒茶」
- 玉露の茎茶は「雁が音(かりがね)」と呼ばれ、最近では良質な茎茶の別称となっている
芽茶(めちゃ)
出物に含まれている、茶葉に成長できなかった芽(芽先・めんざい)部分は「芽茶(めちゃ)」になる。
- 小さいので高温でさっと淹れる
- 葉が開ききるまで何度も淹れられる(煎茶は2~3回ほどで滲出しきるが、芽茶は一般的にそれ以上いける)
- 濃厚な渋味と香り
粉茶(こなちゃ)
出物から茎や芽先(めんざい)を取り除いて細かく残ったもの。
- 小さく細かいのでお茶を淹れる際に蒸らす必要なく、茶こしにお湯を入れてすぐできる(=急須不要!)
- 寿司屋のお茶、あがり、ティーバッグの中身はこれ
回転寿司などでも出てくる粉のお茶はこれです!
最後にちょこっと
記事の閲覧ありがとうございます!
一言で簡潔にわかる形を意識してまとめてみたのですが、いかがでしょうか?(むしろもっと情報あったほうがいいのかな・・・)
ご意見や「こういうのも書いて・教えてー!」などあればお気軽にコメントいただければ嬉しいです。
本日ご紹介したお茶は、生産方法や製法よって上記のように種類が変わってきます。
お茶の樹が一緒といえば、紅茶・中国茶・日本茶は全て同じチャの木からできているんですよ!それについては下記記事も是非☆
 お茶の違い解説!日本茶・緑茶・紅茶・中国茶・プーアル茶は何が違う?
お茶の違い解説!日本茶・緑茶・紅茶・中国茶・プーアル茶は何が違う?