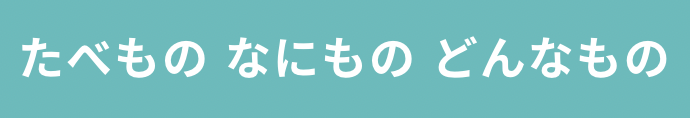こんにちは☆
管理栄養士で日本茶スペシャリストの田代です!
日本に住むみなさんはペットボトルのお茶も含め、緑茶(煎茶や抹茶、焙じ茶、番茶など含む)を飲む機会が多いでしょう。
最近、お茶のペットボトルで「体脂肪を減らす」など謳われた商品が増えてきましたが、実はダイエット以外にも美肌効果・ウイルス予防・リラックス・疲労回復・貧血予防・抗アレルギー作用・脳の覚醒・腸内環境改善など様々な効果があります。
日本に伝来してきたのは遣隋使ごろで、そもそもは薬としての扱いだったんですよ!
本日は緑茶の成分と効果効能について解説します。
メリットだけでなくデメリット部分も挙げていきますね。
緑茶に含まれる成分

代表的な含有物はカテキン、カフェイン、テアニン、ビタミン群、ミネラル類、サポニン、食物繊維です。
下記がそれぞれの成分の概要です。
| カテキン | 日本茶の苦味成分。ポリフェノールの一種。 ①肝臓の脂肪代謝機能を助ける(→太りにくくなる効果が期待されている) ②食中毒菌への強力な殺菌作用 ③活性酸素消去(=抗酸化作用) ④抗ウイルス作用 ⑤コレステロール上昇抑制(悪玉と言われるLDL-コレステロールを減らす) ⑥抗アレルギー作用(ヒスタミンの抑制) |
| カフェイン | 脳を刺激し頭をすっきりさせる。 (=疲労回復、覚醒作用、大脳刺激、強心作用、利尿作用) |
| テアニン | アミノ酸の一種。 緑茶のうま味であり、特有のまろやかな風味となる。玉露に多く含まれる。 リラックス効果がある。 また、日に当たるとカテキンとなりまろやかな味から一転して渋味を感じさせるようになる。 |
| ビタミン類 | ビタミンA、B1、B2、C、E (A、C、Eは抗酸化作用あり。水溶性ビタミンも脂溶性ビタミンもどちらも含むことも特徴です。) |
| ミネラル | フッ素、カルシウム、カリウム、鉄 |
| サポニン | 鎮静・鎮痛効果 |
| 食物繊維 | 腸内環境を整えることに寄与し、排便を促す |

最近はペットボトルのお茶に「体脂肪を減らす」など機能を記載したラベルが貼られているものが多いですね。
これはカテキンによる脂肪代謝機能向上や、LDL-コレステロール上昇抑制の効果による機能性を謳っているものがほとんどです。
(写真は伊藤園さんのおーいお茶の濃いやつ。これ飲んだことありますか?結構苦味強めなんですよ。カテキンがっつり入ってるな〜!って感じです)
(日本茶スペシャリストの勉強をしている方へ・・・成分や効果について資格試験教材に出てくるのは上記の内容まで。栄養知識がある方であれば上記までの内容で効果についても推測がつきますが、そうでない方も知識の差を埋めるためにもぜひ下記も読んで深めてみてください☆)
緑茶を飲むメリット(健康や美容への効果)

緑茶にはダイエット・美肌効果・ウイルス予防・リラックス・疲労回復・貧血予防・抗アレルギー作用・脳の覚醒・腸内環境改善など様々な効果があります。
「手短に・端的にわかる!」を重視して解説してます。(もっとロジカルに知りたい方は最後に参考文献を見てみてください☆)
ダイエットや肥満予防
カテキンは脂肪代謝機能を助け中性脂肪の低下に作用し、コレステロール上昇抑制をする効果があります。また、ビタミンEにもコレステロール抑制の効果があります。
コレステロールは細分するとLDL-コレステロール(悪玉)と HDL-コレステロール(善玉)に分かれます。血液をドロドロにしたり、血液循環を悪くすることによって代謝を落とし肥満につなげるのがLDL-コレステロールであり、カテキンはこれの排出を促進します。
殺菌作用・ウイルス予防
カテキンの効果で、食中毒菌やピロリ菌(胃癌の原因)などの菌の体内増殖を抑える効果や、抗ウイルス作用があります。
風邪やインフルエンザなどウイルスが体内に侵入した際、ウイルスは細胞に付着しようとします。カテキンを摂取すると付着しづらくなると言われています。
抗アレルギー作用
こちらもカテキンによる効果で、アレルギー症状を抑える効果があります。
アレルギー物質物質が体内に入ってからアレルギー症状発生までの過程で、”ヒスタミン”と呼ばれる伝達物質が体内に放出されます。カテキンはこのヒスタミンの放出を抑制することで痒みやくしゃみ、発疹などアレルギー症状の発生を抑えるのです。
脳を刺激しスッキリ・覚醒
緑茶にもカフェインが含まれ、脳を刺激し覚醒させる作用があります。
カフェインの覚醒作用は、コーヒーでお馴染みですよね。
細胞の老化を抑制する(抗酸化作用)
カテキンおよびビタミンA,C,Eのそれぞれの効果で、細胞の老化を抑制する”抗酸化作用”というものがあります。
鉄が錆びたり、切ったリンゴが褐色化するのと同様で人間の体も歳を追うごとに酸化していきます。私たちが呼吸で酸素を取り入れた際、一部の酸素が「活性酸素」となり、過剰になった活性酸素は細胞の老化(酸化)を促進していくのです。抗酸化作用とはこの酸化を抑制する効果となります
(補足:活性酸素は悪いことばかりでなく、ウイルスや細菌などを攻撃する作用もあります。必要以上に過剰な状態は老化が気になるので避けたいですね・・・)
美肌効果(シミ予防・健やかな肌にする)
ビタミンA、C、E、B2は粘膜維持や代謝への関与が多く、肌を健やかに保つ効果があります。
- ビタミンA:目や皮膚の粘膜を健康に保ち、抵抗力を強める役割
- ビタミンC:コラーゲンの合成に必要不可欠な栄養。コラーゲンは肌や骨などあらゆる細胞の結合に必要なため、ハリのある健やかな肌にはコラーゲンが必要。
- ビタミンE:紫外線や刺激から肌を守り、潤いを保つために必要なバリア機能を安定させる。また皮膚の新陳代謝を高め、メラニン(しみやそばかすの元)の排出を促す。
- ビタミンB2:代謝に寄与し、肌や粘膜、髪、爪などの細胞の再生を促進。 ※疲れ・肌荒れ・口内炎用の製剤として売っているチョコラBBは「ビタミンB2主役製剤」というもので、主にビタミンB2を配合しています!
上記のようにビタミン類は肌を健やかに、美しく戦士達と言えますね!
貧血予防
緑茶には血の一部となる鉄が含まれ、さらにビタミンCには鉄の吸収を助ける作用があり貧血予防に繋がります。
代謝促進・疲労回復
緑茶にはビタミンB1、B2が含まれ、これらビタミンB群は代謝促進の機能があります。
ビタミンB群はエネルギー代謝(摂取した食物や体内の貯蓄エネルギーからのエネルギー産生)を行う時の補酵素として必要で、ビタミンB1は糖質の代謝に、ビタミンB2は脂質の代謝に特に寄与します。
体内循環を良くする
代謝促進の内容と重複する部分もあり、これは直接的というよりは間接的かつ結果的にですが、緑茶に含まれるビタミン群、鉄、カリウムなどは血の巡りなど水分循環も良くします。
ビタミン群が全身の代謝を円滑に回すことに関わり、鉄は健やかな血を作り、カリウムは体内の余分なナトリウムの排出の効果があります。
リラックス効果
アミノ酸の1種であるテアニンにはリラックス効果があります。
リラックス効果のほか、睡眠改善効果、統合失調症やうつ病などの精神疾患の治療や予防に対して有用であることも研究において示唆されています。
腸内環境を良くし排便を促進する
緑茶には食物繊維が含まれ、腸内環境を整え、排便を増やす効果があります。
腸内環境が良くなることは美肌にも繋がります。
その他期待される効果
緑茶を飲むデメリット(眠れなくなる?歯へ着色?)

デメリットとして挙げられるのは下記の2つでしょう。
カフェインの覚醒効果が睡眠を阻害する
メリットのほうでカフェインが脳を刺激しスッキリさせ覚醒させるとお伝えしましたが、これは逆に寝付きづらくするということにも作用します。
これはコーヒーなどでみなさんご存知ですよね。
しかしながら緑茶でのこの興奮作用については、カフェインと逆でリラックスさせる作用のあるテアニンによる相殺でさほど強くないと言われています。
私はコーヒーを夜に飲んでも爆睡なタイプなので(笑)あまり気にしませんが、気になる方は夜にカフェイン強めの飲み物は避け、カフェインレスティーや緑茶の中でもカフェイン控えめ低めの温度で入れたほうじ茶などを飲むと良いでしょう。
お茶の淹れ方で多少カフェインの抽出量を抑えることもできますので、知りたい方はこちらの記事で↓
「(Coming soon)記事:淹れ方で緑茶のカフェインを抑えられる!?」
カテキンは歯に着色を及ぼす
これもコーヒーで起こることと似ておりますが、ポリフェノールの一種であるカテキンが歯に着色を及ぼすことがあります。
緑茶や紅茶、ワイン、コーヒーなどに含まれるポリフェノールが水やタンパク質と結びつくことによって、ステインとして歯に着色を及ぼすことがあります。緑茶の場合は原因となるそのポリフェノールがカテキンです。
カップや急須に茶やコーヒーを入れっぱなしにして茶渋ができた経験はありませんか?あれです!
補足:タンニンって?カテキンとの違い
着色の原因物質として「タンニン」という名が挙げられることがあります。
これは渋味成分を呈するポリフェノールの総称のようなものです。(例えば、緑茶のタンニンはカテキン、ワインのタンニンはプロアントシアニジン。)
現在は緑茶に含まれるのがカテキンと特定されていますが、まだ今ほど研究が進んでいない昔から革製品を作る際に不要なタンパク質を除去するために使う植物由来の物質をタンニンと呼んでおりました。
現在では特定性質の化合物を分類する名称となっています。
良質な睡眠に配慮した飲み方
ここまでで、カフェインが良い意味では頭をシャキッとさせ・ネガティブな意味では寝付きづらくするということをご説明しました。
それでは、睡眠にも配慮した緑茶のおすすめの取り入れ方を紹介します。
ポイントは時間帯やその後の予定ごとで緑茶の種類を変えること!
朝・仕事中・夜鍋して勉強や仕事の時
頭をシャキッとさせたい! ・・・煎茶や茎茶
特に茎茶はフレッシュな味わいなので朝に飲むと清々しい気分になりますよ!
※美味しく淹れる温度に調整する時間がないドタバタの朝などは、ほうじ茶や番茶など高温でサッと淹れられるものが良いです。美味しいお茶を淹れるために疲れてしまっては元も子もないので、日常への取り入れやすさを重視しましょう。
夜、数時間後に寝る時
良質な睡眠を取りたい。・・・低めの温度で淹れたほうじ茶・番茶
ほうじ茶や番茶が手元にない場合でも、煎茶やその他お茶を低めの温度で淹れることで多少カフェインの抽出を抑えることができます。
ちなみに、運動の20〜30分前に飲むと効率良く脂肪燃焼できる効果が期待できますよ☆
余談:ウイルス予防のお茶うがい
また、小学生などの頃に「お茶うがい」を経験したことがありますか?
静岡県民の私はもれなく経験しました!他県の友人も経験したとのこと。(水筒にお茶をいれて学校に持っていき、それでうがいをします。風邪やインフルエンザの時期に学校全体として行なうことがあります)
この「お茶うがい」はカテキンによる殺菌作用や抗ウイルス作用を活用しようというものです。
ご家庭でも帰宅時に手洗いとセットでお茶うがいをやってもいいですね!
「(Coming soon)記事:お茶うがい用に効果的なお茶の種類・淹れ方は?」
参考文献:
- 文献1:栄養の基本を知ろう!栄養教養学部(大塚製薬/大塚製薬栄養素カレッジ)
- 文献2:Formie 日本茶スペシャリスト教材(日本能力教育促進委員会(JAFA)主催)※有料教材。購入にて閲覧可能。
- 文献3:カテキンの種類と効果と摂取量(公益財団法人長寿科学振興財団/長寿ネット)
- 文献4:テアニン(わかさ製薬/わかさの秘密)
- 文献5:ビタミンCが足りないと老化が進む!?(地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター/研究トピックス)
- 文献6:お茶の成分と健康性 カテキン(伊藤園/お茶百科)
- 文献7:色と化学のQ &A(キリヤ科学株式会社/企業HP)
- 文献8:ほうじ茶を飲むと歯が黄ばみやすくなる?(湘南美容クリニック/歯の黄ばみに関するコラム)