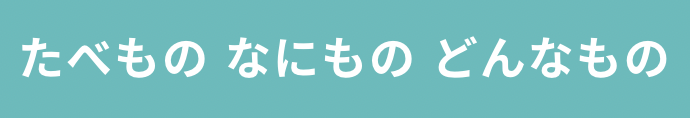こんにちは!日本茶スペシャリストの田代です。
本日は日本茶関連でよくある疑問「八十八夜」について。
八十八夜といえば、「夏も近づく八十八夜〜」の歌詞で始まる”茶摘み歌”でお馴染みかと思いますが、八十八夜っていつのことかわかりますか〜?
日本人の教養的な内容なので、忘れた!という方は一緒におさらいしましょう!
八十八夜って何?いつのこと?
八十八夜とは、立春から数えて88日目のこと。毎年5月2日か1日がほとんどです。
茶摘みは一般的に4月下旬〜5月にメインとなる一番茶の茶摘みを行いますが、
八十八夜の日に摘むお茶は栄養価が高く、不老長寿の縁起物とされています。立春は春の始まりと言われており、国立天文台の観測によって「太陽黄経が315度になった瞬間が属する日」と定めているそうです。(簡単に言うと、太陽がとある定位置にきたタイミングということですね。)
立春の日は多くの場合2月3日か4日で、それに合わせ八十八夜の日程も変動します。
ちなみに2022年は5月2日が八十八夜でした。来年以降は下記の日程です。
- 2023年 5月2日
- 2024年 5月2日
- 2025年 5月3日
- 2026年 5月2日
「夏も近づく八十八夜〜♪」は”茶摘み歌”
小学校で手遊びとしてやりませんでしたか?この歌は”茶摘み歌”というものです。
今の小学校でも、小学3年生でやる音楽の1つとされていますよ。
茶摘み歌の歌詞
夏も近づく八十八夜
野にも山にも若葉が茂る
あれに見えるは
茶摘じゃないか
茜襷(あかねだすき)に菅(すげ)の笠
日和つづきの今日此の頃を、
心のどかに摘みつつ歌ふ
摘めよ 摘め摘め
摘まねばならぬ
摘まにや日本の茶にならぬ
茜襷(あかねだすき):茶摘み衣装で身につける赤色のたすき
菅(すげ)の笠:菅(すげ)は笠や蓑に用いる草。茶摘み時に日除けで被るの笠のこと
日和(ひより):ここでは晴れた良い天気を指す
歌の由来や発祥。有名な理由は”尋常小学唱歌”だから
明治44年〜大正3年にかけて作られた「尋常小学唱歌」に含まれているために、有名な歌となっております。
尋常小学唱歌とは当時の文部省が定めた小学校教育で利用する歌集で、第一〜六学年まで学年ごとそれぞれ定められていました。
茶摘み歌は現在も小学校3年生で歌う音楽として文部科学省より挙げられています。
・ぽっぽっぽ〜はとぽっぽ〜の「鳩」 や
・あたまを雲の上に出し〜の「富士の山」
・犬は喜び庭かけまわり猫は〜の「雪」
・うさぎ追いし〜の「ふるさと」
・「春が来た」など。
「茶摘み歌」の発祥地は京都宇治で歌われていた茶摘み歌が変化したとも言われていますが、
作詞作曲者共に不明、発祥地も今もわかっていないのです。
茶摘み歌は昔は各地の茶栽培地ごと・茶園ごとにあり、今では歌詞が残されていない歌も多数あると言われています。
では歌についてはここまでとし、
先ほど「八十八夜の日に摘むお茶は栄養価が高く、不老長寿の縁起物とされている」とご紹介しましたが、一番美味しいのも八十八夜なのか?という点に触れていきましょう!
八十八夜に摘んだお茶が一番美味しいのか?

一般的には、味や香りのバランスが取れているのが八十八夜です。
お茶は新芽が出てから日が経つにつれ下記の変化が起こります。
- うま味や甘みは苦味や渋味に変わっていき、ほろ苦さを増す
- しかしあまりに若いとお茶としての成熟度自体が不十分
- 茶葉は新芽の出たてほど柔らかく、だんだんと硬くなっていくこともお茶の味に影響する
上記を総合的に見たときに、八十八夜あたりが一番バランスが良いとなります。
しかし栽培地や茶園ごと栽培方法や製法に特色があり「美味しさ」そのものが異なるのと、そもそも国内でも地域で気候の違いがあるため
八十八夜の日で摘むのが一番美味しい!と一概にはなりません。縁起がいいとされているという点では八十八夜のお茶が一番です。
八十八夜近辺は茶摘み体験に行こう!
八十八夜は毎年5月1日か2日とお話ししました。
これってちょうどGWあたりなんですよ!
GW中どこも混んでるし、今年はどうしようかな〜と考えているそこのあなた!のんびり茶摘み体験はいかがでしょうか?
茶摘み体験の醍醐味は下記です。(個人的感想です。笑)
- 鮮やかな緑が広がる茶園風景に清々しい気分になれる
- 茶の勉強になる
- 新芽の指感触がしっとりやわらか気持ちいい
- 茶摘み衣装が可愛い・小さな子供が着るのはさらに可愛い・・・!
- 茶園風景と衣装がSNS映えして友人との話題になる
実際に茶摘み体験をしてきました!
体験レポや体験施設についてはこちらの記事にて↓
(Comingsoon:茶摘み体験レポート!GWは茶摘み体験に行こう)