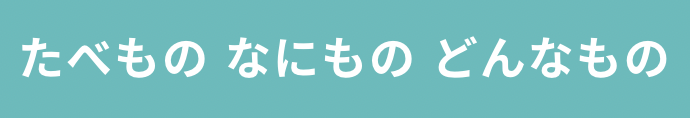こんにちは!日本茶スペシャリストの田代です。
本日は日本茶の歴史について。
ちなみに日本茶とは日本で生産されているお茶の総称で、その中には緑茶・ほうじ茶・抹茶・番茶など色々な種類を含みますよ☆
皆さんお茶はよく飲むと思いますので、歴史を知っておけばより興味を持ってお茶選びができるかもしれませんね。
日本茶の発祥から、年表もつけて解説していきます。
日本茶の歴史:全体の流れ
まずは全体の流れから。年表式にして紹介しますね。
| 奈良時代 平安時代 | 日本茶は中国から伝来したのが始まり。 805年や806年あたりの遣唐使で伝来したというのが有力な説。 実際に茶という言葉が記録として登場するのは815年の日本後記 *活躍者:最澄・空海 |
| 鎌倉時代 | 抹茶文化が普及。 この頃お茶の木が各地に広まり、京都で宇治茶が誕生。 *活躍者:栄西禅師・明恵上人・聖一国師 |
| 室町時代 | この時代から、闘茶(とうちゃ)や茶寄合(ちゃよりあい)など、茶をイベント的に楽しむようになる。 15世紀後半:1486年 禅を基礎に出来上がった侘茶の基礎「四畳半の茶の湯」ができる。 これが後の茶道の土台となる。作ったのは村田珠光(むらたじゅこう) ↓ 千利休がこれを引き継ぎ、さらに広める 16世紀末:「茶道」が完成 この頃、お茶が経済の一端を担う *活躍者:村田珠光・千利休 |
| 江戸時代 | 17世紀中頃:1654年 釜炒り煎茶の文化が改めて中国から伝わってくる ↓ 〜この辺りから庶民もお茶を楽しむ〜 抹茶の製法を応用し、煎茶の製法を確立 ↓ 煎茶が確立してからさらに100年後、玉露が発明される *活躍者:隠元禅師・永谷宗円・山本嘉兵衛 |
| 明治時代 | 鎖国の解禁に伴い、日本茶を海外に輸出するようになる それに合わせて大量生産が必要になり、機械化が進む。 |
| 大正時代 | ー |
| 昭和時代 | 高度経済成長に伴う高級志向で国内の消費量が上がり、大衆茶用の輸入を始める |
各時代で活躍した人々については次の章で個別に解説していきますが、ざっと全体の流れを本章で確認してください。
この計10人が現在の日本のお茶文化を確立した代表的人物です。まずは六茶人から紹介していきますね!
中国から日本へ茶をもたらし広めた6人の人物「六茶人(ろくちゃじん)」

六茶人は中国から日本に茶を持ってきて、各地に広がる段階の人たちです。
遣唐使として中国へ渡った方々、お茶の種を持って帰ってきがち!各自帰国後茶園を作って日本で茶を広めます。
では下記にてざっと詳細を。覚えやすいように各人に独自のキャッチフレーズをつけました!
最澄(さいちょう)
中国から日本へお茶の種(実)を持ち帰った、日本茶発祥の人。
歴史の教科書でお馴染み、遣唐使に行き天台宗を広めた人です。
最澄は中国の天台山からお茶の種も持ち帰り、現在の滋賀県比叡山に蒔きました。
これで日本茶発祥地となる「日吉茶園」が誕生します。
日吉茶園とその近辺で採れる滋賀県の朝宮茶は上記が起源となります。
空海(くうかい/弘法大師こうぼうだいし)
お茶を楽しむ心を持ち帰った、平安時代のカフェ男子。
空海も最澄と一緒に歴史の教科書で登場することが多いですよね。同じく遣唐使として中国へ渡った一人です。空海は弘法大師とも呼ばれ、真言宗を日本で開いた人物。
遣唐使から帰国する際、空海は物理的なものだけでなく”お茶を楽しむ心”も持ち帰ってきました。
空海が書いた詩文集「性霊集」にもお茶に関する詩が多く入っています。
中国へ渡っている最中お茶文化にハマったのかな・・・平安時代のカフェ男子ですね。
空海が持ち帰ったとされる石臼は奈良の仏隆寺に保管中です。
この仏隆寺の開祖堅恵(けんね)に石臼を与えると同時に茶の製法を伝えたそうで、これが奈良県北東部の大和茶の起源です。
栄西禅師(ようさいぜんし)
自力で渡航し、廃れかけた茶文化も再び日本へ持ち帰る熱意人。
栄西禅師は平安時代末期〜鎌倉時代初期を生きた僧で、臨済宗の開祖です。
栄西禅師の時代には遣唐使派遣の終了から300年近く経っており、渡航には覚悟と自己資金が必要な状態。さらに最澄や空海が伝えた茶文化も廃れてしまっています。
そんな中渡航に生死をかけて宗へ渡りました(目的は大陸の仏教を学ぶため)。2度目はインドまで行こうとしたとか!
帰国時に茶の種を持ち帰り、佐賀県の背振山霊仙寺(せふりざん りょうぜんじ)一帯に植えました。
1202年に臨済宗の拠点として建仁寺で開山。
また日本初の茶書「喫茶養生記」を書きます。ここで茶の種類や抹茶の製法、効用、病に対する用法などを記したのです。
栄西禅師はこのように、遣唐使終了後廃れかけていた茶文化を改めて日本に持ち込み広めました。
明恵上人(みょうえじょうにん)
栄西禅師にもらった茶の種でさらに茶を広め、宇治茶の元祖を作った人。
明恵上人は鎌倉時代前期に活躍した僧で、栄西禅師から宋の仏教文化を明恵上人教えを受けています。
華厳宗の復興を行い、京都の栂尾山高山寺(とがのおざん こうざんじ)で開山します。
栄西禅師から宗の文化を教えてもらった際に茶の種ももらい、その種をもとに高山寺で作った茶園が古茶園です。これが宇治茶の元祖と言われています。
できたお茶は明恵上人が日本各地へ広めました。
聖一国師(しょういちこくし)
植えた場所がめっちゃよかった。静岡のお茶はじまりの人。
1235年に宗へ渡り、1240年に帰国しています。
禅を極め帰国した際、100巻以上の書物を持ち帰り様々な技術を日本に伝えました。
1244年には持ち帰り品の1つである茶の種を静岡県の足久保や蕨野(わらびの)に植えます。
後に静岡県の安倍川上流一帯はお茶の適地と判明し、お茶の味に定評が生まれ本山茶が広まりました。聖一国師が静岡茶はじまりの人です。
隠元禅師(いんげんぜんじ)
「みんながお茶を飲めるように!」茶の大衆化を進めた、六茶人唯一の中国出身者。
六茶人の中で唯一の中国出身者です。
また他の六茶人は平安や鎌倉時代を生きた人物ですが、隠元禅師が生きたのは江戸時代ごろ。
1654年に長崎の興福寺からの依頼で中国禅を教えるために来日しました。
隠元禅師は「釜炒り製法」と、煎茶の喫茶法を発展させます。
当時飲まれていたのは碾茶(てんちゃ。抹茶を粉末にする前のもの)で、高価すぎて庶民は飲めませんでした。これを庶民も親しみやすいようい粉末状に開発したのが隠元禅師です。
茶以外にも中国式精進料理「普茶料理」(上下の席関係なく一同和気藹々と楽しむスタイルの作法)や、寒天・胡麻豆腐・れんこん・もやし・インゲンなど食文化をもたらしました。「インゲン豆」は隠元禅師の名前から来ていますよ!
室町時代に2名の茶人によって茶道は確立される
鎌倉時代に抹茶が出てきた後、室町時代に現在の茶道の土台が出来上がります。
それは「四畳半の茶の湯」を作った村田珠光と、その考えを引き継いだ千利休によって出来上がりました。
村田珠光(むらたじゅこう)
茶道の土台「四畳半の茶の湯」を完成させた人物。
村田珠光は伝記上不明点がまだ不明点が多いのですが、茶道において超重要な人物。
1486年 村田珠光によって、茶道の土台となる「四畳半(よじょうはん)の茶の湯」が完成します。
奈良の生まれの僧で、京で茶の湯、能、立花(りっか・生花のスタイル)、唐物の目利き(からもの・中世〜近世において高価で高位な者が楽しんだ中国からの輸入品)、和漢連句(中国様式と日本様式を合わせた連句)を学び、足利義政の茶道師範となります。
臨済宗の一休宗純(アニメでお馴染みの一休さん!アニメと実際とでは随分違うようですが。)との出会いも経験の1つとなり、侘茶の基礎を作ったのです。
ちなみに「四畳半の茶の湯」の四畳半とは、下記の写真のような畳4.5枚分のスペースです。

なぜその大きさだったのかは明確なところはわかっていませんが、もてなす側である亭主と客が遠すぎることなく、近すぎて緊張しない絶妙な距離感であることや
たくさんの装飾が必要ない広さであることが理由として考えられます。
千利休(せんのりきゅう)
茶道の作法を完成させ、織田信長と豊臣秀吉の茶頭を務めた有名人。
村田珠光が作った四畳半の茶の湯の考えを引き継ぎ、千利休が茶道の作法を完成させます。
千利休はよく耳にしますよね。
千利休が有名なのは茶道の作法を完成させたことに加え、50代の頃に織田信長の茶頭(さどう)を務め、その後は豊臣秀吉の茶頭も担ったという点もあります。
時代を大きく変えた二人の武将に認められ茶を振る舞っていたのです。
※茶頭とは茶の湯の準備や美術品の鑑定・購入などを行うもの。
お茶の大きな転換期を迎える江戸時代。3人の立役者
17世紀中期〜18世紀(時代は江戸時代)、それ以前と比較し茶文化は3人の立役者によって大きな転換期を迎えます。
3人とは、隠元禅師・永谷宗円(ながたにそうえん)・山本嘉兵衛(やまもとかへい)です。
隠元禅師は前章で紹介した通り、釜炒り製法を確立させ釜炒り茶として庶民が楽しめるようにしました。
永谷宗円(ながたにそうえん)
宇治茶の優良品種を開発。現在の煎茶に近い緑色で香り高いものにした。
1738年 永谷宗円は宇治茶の優良品種を作り上げ、現在の煎茶製法に近いものを生み出します。
それまで飲まれていたお茶は色は赤黒く、味も香りも薄め。それを現在の緑色で香り高いものに変わったのはこの頃のことです。
永谷と後述の煎茶商「山本嘉兵衛」の4代目が商談をし、そこから永谷園と山本山の付き合いが始まります。
ちなみにお茶漬けで有名な「永谷園」の祖先は永谷宗円だそうです!(永谷園HPより)
山本嘉兵衛(やまもとかへい)
玉露の製法「覆い下栽培」を編み出した茶商人。
煎茶商として1690年に創業した山本山。代々その後継が山本嘉兵衛を名乗ります。
1835年 6代目山本嘉兵衛が布などをお茶の樹に覆いかぶせて一時的に光を遮断する「覆い下栽培」を編み出します。
これが玉露の製法の完成です。
近代〜現代は発明家による機械化や、海外との輸出入
開国宣言をしてからは、海外輸出がスタート。
明治初期にはなんと輸出総額の約20%が日本茶だったとのこと。海外に対するビッグビジネスですね!
その後どんどん輸出を多くしていき、明治後期には国内生産の60%を輸出していました。
輸出に伴い生産量を増やす必要がでたため、機械化と茶の品質改良が進みました。
- 機械化:発明家の高橋謙三・・・粗揉機(そじゅうき)を発明。手もみ工程を解消。
- 品質改良:品種「やぶきた」が誕生。今でも国内75%以上の茶園がやぶきた。
1960年代の高度経済成長期になると、高級志向が重なり国内消費が増加→今度は大衆茶用として輸入を始めました。
そして現在に繋がっていきます。
終わりに
どうでしたか?お茶に関わる人は歴史の教科書でよく目にする人物ばかりですね。それだけお茶は日本の経済と文化を大きく動かしたものなのです。
上記の歴史的内容は日本茶スペシャリスト教材を元に、私のほうで何点か知識補足をしたものです。
日本茶スペシャリストを受講する方は歴史もざっと理解が必要になるのでしっかり勉強しておきましょう!
それではまた☆