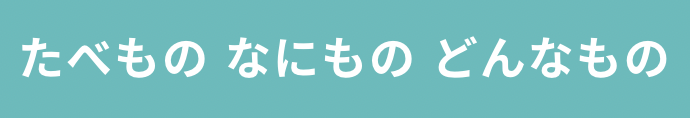こんにちは!
管理栄養士で日本茶スペシャリストの田代です。
本日はうがい用のお茶について。
その前に、皆さん「お茶うがい」って知ってますか?
お茶には抗菌作用や抗ウイルス作用があり、風邪やインフルエンザ予防のためにお茶でうがいをするというものです。
筆者は小学生の頃、学校全体で冬に家庭から水筒でお茶を持参しうがいを行うという季節の風習(?)がありました。
喉の痛みを感じてお茶うがいをする方もいるでしょう。お子様が飲んでしまっても心配がないのも魅力の1つです。
本日はお茶うがいはそもそも効果があるのか?どのようなお茶でうがいをしたらいいのか、おすすめのお茶の種類と、うがい用お茶の淹れ方などを紹介します。
麦茶でも効果があるのかな〜と思っている方!残念ながら麦茶では効果は見込めませんのでご注意です!
お茶うがいとは

お茶うがいとは、風邪やインフルエンザなどの予防のために水ではなくお茶でうがいをする方法です。
学校全体でうがい用のお茶の持参を推奨している小学校などもあり、経験したことがある人も多くいるようです。
筆者も小学生の頃は学校で冬にうがい用のお茶持参を推奨されていました。静岡県民だったのでより一層お茶との馴染みが深いのもあると思いますが、他の県でも実施されていると耳にしています。
市単位で各学校へ推奨をしていたり、学校ごとで方針を出しているようです。
2番目のツイートは2022年のもので、最近でもお茶うがいは学校で実施されているようですね。
お茶うがいの風邪やインフルエンザ予防効果

さて、お茶うがいが果たして効果あるのか?という疑問があるでしょう。
効果があるとされている所以は、お茶に含まれるカテキンです。
現在の研究でも日本茶に含まれるカテキンには殺菌作用・抗ウイルス作用があると明確に結果が出ています。

元々お茶が中国から日本に遣唐使で伝わってきた当時、嗜好品というだけでなくお茶は薬として扱われていました。
ただし!実際お茶で”うがい”をする検証については正しく条件を整えて行なった実績がなく、不明瞭なのが実際です。
お茶の抗ウイルス作用については、うがいではありませんが飲量とインフルエンザ罹患減少には関連があると発表されています。(※1)
ですので現時点でうがいについては、ただの水よりはお茶でうがいしたほうが良いだろう・しないよりしたほうが良いだろうという感覚です。
またこれは筆者の意見ですが、温かいお茶でうがいすることによって喉を温めるというのも、菌やウイルスの予防に多少効果が上がるのではと思っています。
カテキンの殺菌作用・ウイルス予防
カテキンの効果で、食中毒菌やピロリ菌(胃癌の原因)などの菌の体内増殖を抑える効果や、抗ウイルス作用があります。
風邪やインフルエンザなどウイルスが体内に侵入した際、ウイルスは体内の細胞に付着しようとしますが
カテキンを摂取するとウイルスが細胞に付着しづらくなるとされています。(※2)
<さらに詳細>
一言で「カテキン」と言ってもいくつか種類があり、そのうちエピガロカテキンガレート(EGCG)というカテキンがあります。このEGCGがインフルエンザウイルスのヘマグルチニン(HA)蛋白質に作用し、インフルエンザウイルスを凝集させ、さらに抗体も凝集させ、ウイルスが細胞に吸着するのを防いだと報告されています。
お茶の様々な効果について詳しくはこちら↓
 緑茶の成分。健康・美容への効果とデメリット
緑茶の成分。健康・美容への効果とデメリット
うがい用におすすめのお茶の種類はこれ!

日本茶には煎茶、玉露、ほうじ茶、玄米茶、抹茶、番茶や粉茶など種類がありますが
お茶ならなんでも良い・見込める効果が同じというわけではありません。
ではどのお茶が良くて、どのお茶では意味がないのか?
おすすめは普通煎茶
効果が見込まれるとされているのはお茶に含まれるカテキンが由来のため、カテキンを多く含む茶葉がおすすめです。
見込める効果(=カテキン含量の多さ)+うがいのしやすさを踏まえると、普通煎茶がおすすめです。飲む用でなくうがい用ですので、スーパーなどで安いのを買うので十分です。
※日本茶の種類についてはこちらの記事で↓
 日本茶の種類一覧!14種の製法・特徴・違い
日本茶の種類一覧!14種の製法・特徴・違い
麦茶やほうじ茶では効果は見込めない

ほうじ茶や麦茶で代用してしまう方が時々いるようですが・・・
前章の注意書きで、うがいに適さないお茶としてほうじ茶や麦茶も記載しました。
ほうじ茶は煎茶とは異なり、製法で「焙じる」(カラカラになるまで炒る)工程を踏むことでカテキンなど各種成分を少なくしています。緑茶の渋味はカテキン由来ですが、ほうじ茶は渋味が少ないですよね。
また麦茶はチャの木の茶葉ではなく麦で作ったお茶。カテキンを一切含んでいないため効果を見込めません。
それではここからもかなり大事なお話しで、うがい用としてお茶を入れる際のポイント・コツがあります!
<重要>効果を得るためのうがい用お茶の淹れ方

淹れ方のポイントは1つ!
お茶を淹れる温度を、80℃以上の高温にしましょう。
※ただし、そのままうがいすると火傷する恐れがあるのでお茶を淹れた後は冷ますようにしてください。
(これは筆者の独自意見ですが、冷ましつつ、適度に暖かいほうが喉を温めるため良いかと思います。)
抗菌や抗ウイルス作用はお茶に含まれる”カテキン”の作用から由来しています。
化合物ごとで抽出しやすい温度というのがあり、カテキンの抽出温度は80℃以上です。(※4)
それ以上の温度、例えば沸騰直後の100℃近くなどの温度で淹れるとカテキン量が減ってしまうか?という疑問については、現時点の研究での答えは「減らない」です。
カテキンには種類があり、温度によって異性化という化合物の変化が起こり他の種類のカテキンへと切り替わったりしますが、カテキンの総量としては80~100℃ではほとんど変わらないとの結果が出ています。(※5)
なので「80℃に調整しなくちゃ!」と神経質にならず、お茶を淹れて大丈夫です。お湯の温度を調整するのって面倒ですものね・・・
カテキンは渋味を持っているため、たくさん抽出すると渋く苦いお茶が出来上がります。今回はあくまでうがい用なので高温での抽出をおすすめしますが、飲む用としての煎茶では、渋すぎずアミノ酸のうま味を抽出できる70~80℃の温度がおすすめです!ダイエット用で渋くてもカテキン多めがいい場合は、うがい用同様で高温で淹れるのが良いでしょう。
適切な抽出温度に調整する簡単な方法・コツ
簡単に淹れられるコツをお伝えします。
お湯は器に移す毎に約5~10℃下がると言われています。(器の温度や気温にもよります)
一旦お湯を沸かしたやかんやケトルから水筒に移し→ それを茶葉の入った急須に移し替える(お茶を淹れる) と2度移し替えたことになるので10~20℃下がることになります。
=80~90℃で抽出することとなり丁度良い温度です。
最後に
いかがでしたでしょうか?
今回は「うがい用」のお茶の淹れ方について触れましたが、飲む用のお茶の美味しい淹れ方についても別記事で解説しますね。
ぜひそちらも見てみてください☆
(Comingsoon:「煎茶の美味しい淹れ方」)
参考文献