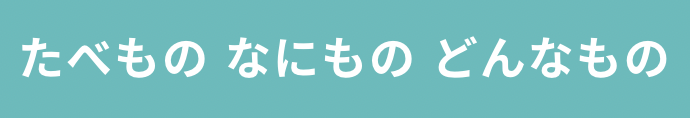こんにちは☆
元大手食品メーカー勤務、たしろです!
私は最初は開発へ配属、その後異動で営業(商品設計も行う企画営業)部門へ配属となり大きく2つの部門を経験しました。
本日はそのうち開発のほうで働いた経験について、リアルに書いていこうと思います。
ちなみに私は管理栄養士の資格を持っていますが、開発になるにあたって資格が必要なわけではありません。
食品メーカーで勤務することに興味のある方の参考になれば幸いです!
筆者基本スペックと就職した食品メーカーについて
筆者の基本スペック
地方公立大学出身。食品系の学科で管理栄養士取得。理系の学部卒。大学院は行っていません。
高校の頃から食品メーカー勤務を目指して大学進学し、就活はもっぱら食品関連。
大学入学当初は開発職を目指していましたが、アルバイトでの接客経験を通じて営業職へ志望転換。就活も営業志望で行なっていました。
就職した食品メーカーはどこ?
食肉加工業界5番手のメーカー。
業務用食肉・ハム・ソーセージのほか、グループ内に様々な工場を抱え多種多様な加工食品を製造。
本体従業員人数800名ほど、グループ連結で1500名ほど。
就職背景(「これをやりたい」という意思を持って就活に臨む)
私の地元に就職した企業の地方本社があり、子供の頃からそこの商品に馴染みがありました。
大学で地元を出た時、その商品が県外のスーパーに置かれていないことに気が付いた時は衝撃で(全国展開の企業だと思っていたので)、「なんであんな美味しいのに売られてないの・・・!?」とびっくりしました。なので実家の母にわざわざ宅配で送ってもらって、家に友達を呼んでその商品(ウインナー)を使って料理を使ったり。
上記のことは就活の面接の際に人事に話し、
さらに「私はもともと開発志望で大学進学しましたが、御社はこんなにも美味しい商品を持っているのに広まっていないのは営業力がまだ弱いからなのかなと思いました。なので私は今も商品開発に興味はありますが、営業として商品を広めたいです。」と伝えました。
随分とハッキリした物言いですが笑、真摯に本音を話したのできっと失礼には当たらなかったと思います。
(ちなみにその際人事のコメントは「まさにその通りなんですよ。営業力が課題で。」)
そして合格し就職に至ります。
つまりは就活当時からその企業に入社したい明確な理由を持っておりました。
開発の仕事(全体像・日々のこと)

開発の仕事は大まかにいうと下記4つです。
- 自社ブランド既存商品のアップグレード(より良くする)
- 自社ブランド新商品開発
- 法人顧客のブランドの中身を開発 及び アップグレード
- 例えばイオンや7&iの独自ブランド(=プライベートブランド/PB商品といいます)の中身をイオンや7&iへ提案し、作っているのは各食品メーカーです。
- ファミレスの食事や、ディ○○ーランド・シーの食事なども、ファミレスやランド・シー自体は食品製造の知見や機能があるわけではないので食品メーカーが製造や提案をします。
- 営業や商品企画の部門が利用する用のサンプル作成
上記に付随して生じるのが下記。
- 本当に僅かずつ原料の量を変えて商品として適切か検証
- 工場現場に入り、工場のラインでの製造に落とし込めるか検証(開発室内にも工場と同設備の機器があることが多いですが、実際に広々とした工場で大量生産するとなるとまた同じように行かないこともあります。例えば商品がライン上を流れていく中、機械と機械の間の受け渡しでうまく行かなかったり、実際の工場設備で入れるとほんのもう少し生地の水分量落とさないとうまく整形されないなどなど)
- 工場で検証を行うためには、事前に工場の担当と調整し実製造の合間にラインを貸してもらわなければなりません。
- 製造機械の選定
- 原料それぞれ何gなのか、細かい表を作成(営業さんに持って行ってもらうサンプル用でも都度作成したり。)
- 営業さんが営業するにあたっての商品のPRポイントを擦り合わせる(例えば、特殊な原料を使っている、独自の製法を行っている、他社品との違いなど
- 原材料の調達先の選定(仕入れ先が1箇所ではリスクがあるので、常に複数を検討します。原材料調達の専門部門があることもあり、そことの連携の必要があります)
- 法人顧客を招いて商品や会社のプレゼンをすることもあります。その際のプレゼン用商品を作るのはもちろん開発です。見栄えも大事で、盛り付けセンスなども問われます。
などなど正直書ききれないですが、わかりやすいものだとこの辺りです。
ちなみに検証として作っている過程で何かミスしたら(例えば水の量を間違えたり、機械の稼働時間を間違えたり)、また一から作り直しです。
大学で理系の研究室にいらっしゃる方は、ミスったらまた作り直して長時間かかる・・・みたいなのイメージしやすい方多いかもしれませんね。
大体の所、商品カテゴリーによって担当が分かれることが多いです。ハムならこの人、ソーセージならこの人、麻婆豆腐といえばこの人など。
各担当が作った毎日の試作品は全員で検食し意見交換しますが、新人の私と同僚は、正直「前回よりもーーを0.3g減らしました」という試作品を食べてもイマイチ違いがわからず日々苦戦しました。笑
でも考えながら味わう訓練を重ねることで、だんだん舌が敏感になっていき、違いがわかるようになっていきます。
食品メーカーの開発で楽しいこと・やりがい

楽しいと感じることは人によって違うと思いますが、
一番のやりがいは、自分の開発した新商品が市場に出回ることといって間違いないです。
他には、営業さんなど開発とかけ離れた部門から頼りにされること、食品化学に基づいて論理的に考えものづくりをすることなどもやりがいだったり、人によっては「好き!」と思える点でしょう。
食品メーカーの場合は皆さん何より「食べ物が好き!」という前提で入社すると思うので、これは開発に付く皆に言えると思いますが食べ物を作れるというがシンプルに楽しいです。
私は食品化学系のこと(Aを加えて加熱したからBの反応が起こって、結果こういった仕上がりになる等々)を考えるのが好きなので、こういうことを考えながら商品を作るのも楽しかったです。
私の知人は他の食品メーカーでインスタント麺の開発職に就いていますが、
ラーメンが好きすぎて好きすぎて、何年経ってもいつも「楽しい」と言っています。
オプション的楽しみでは、リサーチのため会社経費で飲食店を巡ることもあるのでそれも楽しいでしょう。(ただし開発を担当した商品の参考のため行く場合も多く、その場合はテーマが決まっているためメニューのうち自分が食べたいと思うものとは限りません。)
食品メーカーの開発で大変なこと
これも個人によるためあくまで私の場合です。
- 営業職などとは異なり、やはり特定の室内に篭りがち。
- 原料のほんの僅かな違い(例えば量で言うなら0.1g変えてみたとか)を常に検証するので、根気が必要でかなり地道。
- 上記の理由で飽きっぽい人には向かないかも。大体商品カテゴリーごとで担当することになるので、コロコロと取っ替え引っ替えいろんな商品に携わるわけではありません。
- 化学系が理解しずらい文系脳の人には難度が高い。
- 色々な味わいを食しているうちに、どれが美味しいかわからなくなってくる。(これは私の未熟さですが笑、おそらく皆最初の数年は経験するのではと・・・。)
- どういう配合でどういう工程で作ったのか、逐一記録を残す必要があるので日々マメな事務的作業も多い。
- 既存商品の原料を変えるなどの程度ならまだマシですが、完全新商品で新しく工場にラインを作るとなると大大大忙し!
どんな人が開発に向いているか
開発での実体験を通じて、どんな人が向いているか感じたことです。
- 地道にコツコツと行うのが好きな人/大きな苦でない人
- 浅く広く物事を知り体験したいタイプ < 1つのことについて深く追求を重ねたいタイプ
- 化学的思考も必要となるので理系科目が得意なほうが仕事が苦でない
私は逆にどちらかというと浅く広く知り体験したい・色々なところに出歩き多方面に足を運びたいタイプで、
大学で食品化学分析系の研究室に所属した際も、実験室という1つの場所に籠るのが好きではありませんでした。
(それもあって大学入学当初考えていた大学院進学はやめ、就活も営業を志望しています。)
化学的ことを考えたり、そもそも食品がめちゃくちゃ大好きなので開発職も好きでしたが、私の場合はその後経験する営業職が天職だと感じました。
就活のポイント:取り繕っても無駄。自分が本当に好きだと思う企業を探せ

最後に、食品メーカーへ就活を考えている方へアドバイス。食品メーカーや開発職に限らずのお話しになりますが、とても大事な点です。
学歴や大学名重視か?
答えはNO。まず食品メーカーは人気の業界の1つで倍率が高いことは確かですが、「有名大じゃないしその時点で自分はダメだ・・・」なんてことはありません。
有名大や偏差値の高い大学出身のほうが履歴書が目立つのは確かですが、現在は昔のような学歴社会ではありません。
また正直言って実際会社に入ると学歴高い人のパフォーマンスが高いかというとそんなことはありません。(逆に有名大卒業で地道に勉強してきた人が、勉強しかしてこなかったが故にあまり臨機応変な対応が取れなかったり、「やり方」に囚われすぎてしまうケースだってあります。つまりは学歴次第ではなく人によるのです。)
その辺りは人事もこれまでの経験でわかっているものです。
むしろ未だに学歴ばかりに囚われているような企業でしたら、だいぶ体質が古いのでそこに就職して未来を開きやすいかどうか・・・が心配ですね。
本当に大事なのは、自分自身の中に「その企業で働きたい」確かな理由があるか
私は食品に絞って色々な企業に応募をしましたが、やはり「大手食品メーカーだから」という理由だけでの応募は所詮見破られます。
なぜそこで仕事をしたいのか、どうして自分はそう思っているのか?を自分自身に嘘をつかず尋ね、面倒がらずに心からしっくりくる答えを探してみることです。
とはいえ色々な企業へ応募をしたり、面接に進んでみたりで「量」を積むのは非常に大事だということを確信を持ってお伝えします。
その過程で色々な企業の情報を得たり、自分を振り返るため、
自分の好みややりたいことが明確化され、曖昧だった自分の形がはっきりとしてくるのです。
そしてその際に積んだ行動量は社会人になっても必ず生きてきます。スキルがなくても行動量を詰める人は、最終的にはなんだってできるようになりますよ!
でもどんなに頑張っても何をしたいのかわからない人もいるでしょう。
そういう方はきっと、自分の好き嫌いを理解するだけの体験と、自分で意思決定する経験がまだ少ないのだと思います。
新卒で就職する会社を決めるのは、言ってもまだまだ経験の浅い学生の状態での意思決定。1社目の会社で様々な経験を積んで初めて物事が見えてくると言って過言ではありません。
はっきりとした「好き」「やりたい」がわからなくてもくよくよせず、少しでも興味があって自分を高められそうな会社でとにかく経験してみるのが良いかと思います。