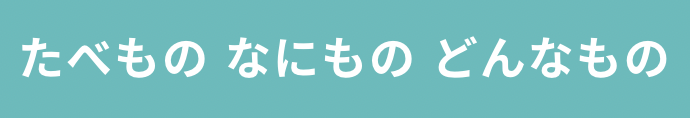夏になると食中毒のニュースをよく目にしますね。
夏に多い各食中毒の原因・症状・予防方法、食中毒の可能性があるときの対応方法について解説していきます。
夏に食中毒が多い原因は”高温多湿”

多い時期:5月〜9月
前提として、年間を通して食中毒菌やウイルスはどこかしらに存在します。
夏に特に食中毒が多い原因は、高温多湿で菌が増えやすい環境のためです。食中毒菌はひとや動物の体温(30~40℃)ほどの温度で最も活発になり、夏の気温は菌やウイルスにとって丁度良い温度です。
発生頻度が高いものカンピロバクターとノロウイルス。ノロウイルスは冬だけでなく実は夏も多いです!
夏に多い食中毒。潜伏期間・症状・原因
症状はどれも大体のところ腹痛・下痢・吐き気・嘔吐・発熱。
発熱が発生しない傾向の食中毒もあるので、食べたもの&症状次第でどの食中毒かある程度予測できることもあります。

潜伏期間通常8~48時間(1~7日と長いケースもある)
存在箇所や原因食肉の腸内にいる菌。鶏肉・豚肉・それらの加工品。特に鶏肉の不十分な加熱!
症状下痢、血性、腹痛、発熱、頭痛、悪心、嘔吐。3~6日続く。
予防方法通常の加熱で死滅。加熱な不十分な鶏肉で食中毒の発生が多いため、よく加熱する。
稀に感染数週間後に、手足の麻痺・顔面神経麻痺・呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」を発症することも。

潜伏期間24~48時間
存在箇所や原因カキなどの二枚貝の喫食。
症状腹痛・下痢・吐き気・嘔吐・発熱。発熱は軽度
予防方法気になるようなら生食しない。

潜伏期間8~48時間
存在箇所や原因主に卵の表面に付着しており、生卵・半熟卵のような加熱不十分な卵から感染。
症状悪心や嘔吐の症状の後、数時間後に腹痛や下痢となることが多い。
予防方法加熱しても死滅しないので、作ったら速やかに冷やす。

潜伏期間1~5時間
存在箇所や原因ヒトの喉や鼻など、身近に存在。手に付いていたブドウ球菌が食物へ付着し増加・毒素産生。おにぎりなどに。
症状腹痛・下痢・吐き気・嘔吐。発熱はほぼなし。重篤になることが少なく、数時間〜2日で症状が改善することが多い。
予防方法付着してしまうと加熱しても産生された毒素までは死滅しないため、①付着させない(手をよく洗う・傷や手荒れがあるひとは直接触らない)、②室温放置せずに保存は冷蔵庫へ、③作ったらなるべく早く食べる

潜伏期間3~8日
存在箇所や原因ハンバーグなど加熱不十分な牛肉
症状水様便・腹痛・下痢・吐き気・嘔吐・発熱・血便。潜伏期間後、水様便で症状が始まることが多い。死亡や重篤化の例もある。
予防方法加熱で死滅するため、十分に加熱する。

潜伏期間6~18時間
存在箇所や原因動物の腸管・土・下水などに存在。カレーやシチュー・スープなどの煮込み料理、大量に調理された後に長時間室温で保管された食品での発生が多い。
症状腹痛・下痢。発熱や嘔吐の発生はあまりない。下痢は1日1〜3回程度のケースが多く、水様便と軟便。 腹部膨満感
予防方法増殖してしまうと加熱しても死滅しないので、作ったら常温放置せず速やかに冷蔵庫で冷やす。

潜伏期間8~24時間(短いと2~3時間というケースも)
存在箇所や原因寿司や刺身等の非加熱の魚介類
症状腹痛・下痢・発熱・吐き気・嘔吐
予防方法4℃以下ではほとんど増殖しないので、よく冷やす。塩分濃度3%ほどでよく繁殖するが、水では繁殖しないので水でよく洗う。

潜伏期間嘔吐型30分〜6時間、下痢型8時間〜16時間
存在箇所や原因土壌に存在し、米や小麦などの穀類に付着。チャーハンやピラフ等の米飯、スパゲッティや焼きそばなどの麺類が原因の食事となるケースが多い。
症状嘔吐型は吐き気・嘔吐。下痢型は腹痛・下痢。
予防方法常温放置で増殖するため、調理後は速やかに冷蔵庫へ。
セレウス菌には嘔吐型と下痢型があり、日本人には嘔吐型が多い

潜伏期間通常1~2週間(数日〜90日程度に幅広く変動もある)
存在箇所や原因土壌、河川水や家畜、家禽、野生動物など自然界に広く分布。食品の製造ラインに付着することも。加熱殺菌していないナチュラルチーズ、肉や魚のパテ、スモークサーモン、生ハムなど。
症状発熱・頭痛・嘔吐がメインで、次いで腹痛・下痢。
予防方法リステリアは4℃以下の低温でも繁殖するので、開封したらなるべく早く期限内に食べ切る。保存する場合は冷凍庫保存する。加熱で死滅するため、加熱も手段の1つ。
他食中毒と比較すると発生頻度は少なく、無症状の場合も。しかし発症すると重篤化するケースが多い。
妊娠中に感染すると胎児に影響があり、出生後死亡するケースも。

潜伏期間数時間〜十数時間
存在箇所や原因サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類。刺身などの非加熱または加熱が不十分な魚介類の食事。
症状みぞおちのあたりに激しい痛み・悪心・嘔吐
予防方法加熱して食べる。時間が経たないうちになるべく早く捌く。
アニサキス幼虫は長さ2~3cm、幅は0.5~1mmほどの、太めの白い糸のような見た目。生や加熱不十分な魚介類で摂取してしまうと、胃壁や腸壁を刺され、激しい痛みを伴います。
通常は魚介類の内臓にいるため刺身などの場合は撤去されますが、寄生している魚介類が死亡し時間が経つと内臓から筋肉へと移動してきて、かつ目視確認で撤去できなかった場合に食中毒事故となります。
ポイントは①鮮度の徹底、②すぐに捌けない場合は冷凍もしくは加熱、③目視確認。
食中毒は予防できる!自宅での予防方法は簡単シンプル

自宅での食中毒の予防は、簡単なことです。
要は下記を徹底できれば問題ありません。
- 常温放置しない・魚は生で食べる時はすぐに捌き内臓と切り離す
- 加熱する料理はしっかり加熱する
- 早めに食べる
また食品を触ったり調理するとき、食べる時はよく手を洗いましょう。
また、下記のような場合はもうその料理は食べないようにしてください。
- 春夏に常温で数時間放置してしまった
- 調理から時間が経った後、普通と異なる匂いがする(酸っぱい匂い・腐敗臭)
- 調理から時間が経った後、見た目に普通とは異なるネバつき・ヌルつきが出ている
食中毒菌が食材に付着していたとしても、食中毒を生じるほど菌が増えなければ大丈夫です。ですがそもそも”つけない”というところから心掛けるのが大事ですね。
- 食中毒菌は手や、食材にそもそも付着しています。鼻を噛んだり、トイレに行ったり、おむつを替えたり、動物を触った後は手を洗う。
- 調理前に野菜などの食材はよく洗う
- 焼肉などの時は、生肉を触ったトングや箸で焼いた肉を触らない
調理する人も、食べる本人の手にも食中毒菌が付着していることが考えられるので、調理中のこまめな手洗い・食べる前の手洗いをしましょう。
- 冷蔵庫・冷凍庫で、低温で保存する
- とはいえ冷蔵庫を過信せず、早めに食べ切る(冷蔵庫に入れていても、徐々に食中毒菌は増えます)
多くの食中毒菌・ウイルスは人間や動物の体温程度(30〜40℃)で最も活発になります。夏場の気温は食中毒にとって丁度良いのです。
低温であれば増えない菌がほとんどなので、食材や料理は速やかに冷蔵庫への保管へ移行しましょう。
- 食材をしっかりと加熱
- まな板・包丁などの調理器具は洗った後に熱湯消毒
ほとんどの食中毒は加熱で死滅するので、肉・魚・卵の他、野菜もしっかりと加熱すれば安全に食べられます。
目安は食材の中心温度が75度で1分間の加熱です。
まな板や包丁などの調理器具も洗っても菌が残る可能性があるので、洗剤で洗った後に熱湯をかけて殺菌します。
食中毒かも!どうしたら良い?対応方法

「具合が悪く、普段ありえないような嘔吐や発熱、急な下痢・腹痛がある。食中毒かもしれない!」そんな時は、大変かもしれませんが下記の対応をしましょう。
- 水分摂取。できればポカリスエットのようなスポーツドリンク。
- 内科を受診する。発熱がある場合は現在コロナ禍のため、事前に病院へ電話。電話時に他の症状も伝える
- 食中毒になるような原因行動の覚えがある場合は、受診時に医者に伝える(常温放置したカレーを食べた、十分に加熱せず肉を食べたなど)
- 症状発生者の嘔吐処理などした周りの人は、よく手洗いうがいをする
下痢や嘔吐・発熱があると脱水の危険性を伴います。水分を飲んでも吐いてしまうこともあると思いますが、脱水を防ぐため少量ずつ口に含むなどして摂取しましょう。
まとめ:食中毒菌はかなり身近に存在するが、予防できる
食中毒菌は土壌や人の手、食材にかなり身近に存在します。
ですが手を洗う、常温放置しない、しっかり加熱する、すぐ食べるなどシンプルなことで予防が可能です。
子供やお年寄りは重篤化することもあるので、周りの身を守るためにも予防を徹底しましょう。