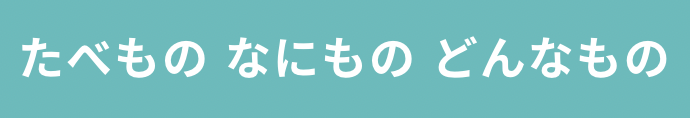桜餅(さくらもち)は日本の伝統的な菓子の一つであり、春を代表するスイーツの一つです。桜の花びらで包んだ餅の中にあんこやきな粉を詰めたもので、地域によって異なる種類が存在します。
本記事では桜餅の種類について詳しく説明します。
桜餅(さくらもち)とは?
桜餅(さくらもち)とは日本の伝統的なお菓子の一つで、桜の花びらが使われていることで知られています。
桜餅は餅の中に甘い餡(あん)が入っており、その表面は桜の葉で包まれているのが特徴です。
桜餅に使われる桜の花びらは、桜の開花時期に摘んで保存し、餅に入れると桜の風味が加わります。桜の葉は、食べる前には取り除きますが、香りを楽しむために包んでいるとされています。
桜餅は、春の訪れを感じる季節限定のお菓子として親しまれています。地域によっては、桜餅にさくらんぼを添えるなど、さまざまなバリエーションがある場合もあります。
関東風桜餅(長命寺風桜餅)

関東地方の桜餅は、小麦粉等を薄く伸ばして焼いた皮で餡を包んだもの。
白餡を使った「白桜餅」と、こし餡を使った「赤桜餅」があります。桜の花びらは、塩漬けにして使用し、甘すぎず上品な味わいが特徴です。
また関東風の桜餅は、形状も特徴的。丸いもち米餅を縦に割き、あんこを挟んで葉で包む形状になっています。
江戸の長命寺で働いていた人が隅田川付近に植えられた桜の若葉を活用して作ったものが起源とされ、「長命寺風桜餅」がその別名です。
関西風桜餅(道明寺風桜餅)

関西地方で一般的な桜餅で、もち米を練り上げた「餅皮」に、こし餡を包んでいます。
もちもちとした米の食感が楽しめるのがおいしいポイント。桜の花びらは甘酢漬けにして使用し、酸味が加わったさっぱりとした味わいが特徴です。
別名で「道明寺風桜餅」とも言われ、由来となるのは原料に使う道明寺粉。道明寺粉は大阪に「道明寺」作られていた保存食が由来で出来上がったものとされています。
この関西風の方が全国的に広く馴染みがあるようです。
どちらの桜餅も昔から変わらぬ花見時期のヒット商品

関東風、関西風どちらの桜餅も、花見の時期に花見客に販売し人気となり全国に広まったよう。
現代の人たちが「映えスイーツ」にときめいているのと同様、今では伝統菓子となっている桜餅も発売当初は新しく可愛いスイーツだったに違いありません。
毎年お馴染みの桜餅ですが、そんな古き時代にも思いを馳せながら味わってみるもの風情を感じられることでしょう。
桜餅は、春の季節になるとスーパーや和菓子屋さんなどで購入することができます。皆さんも、ぜひ春限定の味わいを楽しんでみてください。